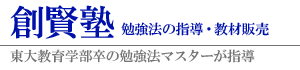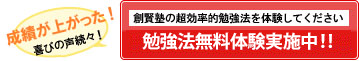数学が苦手な人は「薄くて解説が詳しい問題集」を選びましょう。得意な人は好みで選べばよいでしょう。
1.青チャートは終わらない
1.1.青チャートを習得できるのは数学が得意な人だけ
問題集を選ぶとき、多くの人は青チャートのような500ページ前後もある、大部の、問題パターンを網羅した問題集を選ぼうとします。しかし、こういう厚い問題集をマスターする(全問題をスラスラ解けるようにする)ことができるのは、偏差値65以上で、勉強時間が毎日1.5~2時間以上取れて、意志の強い人くらいでしょう。
偏差値55以下の人がこういう厚い問題集を選ぶのはやめましょう。まず、習得できません。
1.2.青チャートは1周で半年以上かかる
青チャートを例に取ると、数学1A、2Bそれぞれ、練習問題(類題)を除いて600題前後もあり、例えば、1日60~90分で4問進める場合、毎日勉強したとしても、各150日(5ヶ月)もかかります。テストもありますし、学校の予習復習・行事もありますので、1回目だけで6ヶ月以上かかり、1年かけても2~3周でしょう。
6ヶ月後に復習する頃には、たいていの人はほとんどを忘れてしまっています。
ぜひ、1~2ヶ月前に勉強した部分を今解いてみて、何割解けるのか、確認してみて下さい。その結果、1回目に解けなかった問題の半分以上解けなかったら、あなたはもっと頻繁に復習をするべきです。また、今のペースで勉強を続けた場合、いつその問題集の1回目が終わるのかを計算してみて下さい。この2つのデータをもとに、問題集の選択と復習頻度を検討することは価値のあることだと思います。
1.3.正解するだけでなく、解答を再現する必要がある
復習時に再現する必要のある内容は、正解までの式だけでなく、図やグラフ、日本語の補足説明も含めます。それらをある程度正確に再現できて初めて正解になるからです。1回目にできなかった問題で、ここまで正確に再現できるようにするには、普通の人には4~6ヶ月は長すぎます。「全問題をスラスラ解けるようになる」など、ほとんど望めません。これは効率の悪い勉強法の典型です。
よって、青チャートの半分以下の問題量の問題集を選ぶのが普通の能力の人にはオススメです。
2.解説が詳しく”薄い”問題集を選ぶ
上記の通り、偏差値が65以上など、数学が超得意な場合を除いて、問題集は解説が詳しく、定評ある”薄い”問題集を選びましょう。”薄い”とは、問題数が少ないという意味です。問題数が少なく、かつ解説の詳しい問題集を選びます。そういう意味では、講義系で解説の詳しい「元気が出る数学」(マセマ)なども選択肢に入ります。
普通の人は、1ヶ月経ったら多くを忘れるようにできています。それが記憶の法則なので、これは変えられません。よって、1ヶ月といわず、まだ覚えているうちに復習するのが良い勉強法です。私はその復習間隔を2週間以内と決めて指導しています。2週間以内に復習すれば、まだ多少は覚えているので、2回目は1回目の5~7割の時間で終えることができます。
3.教材の選び方
3.1.「どの問題集を解くか」より「問題集をどのように習得していくか」が大事
数学でも他の科目でも、「どの問題集を解くか」より、「問題集をどのように習得していくか」という勉強法の方がずっと大事です。定評ある問題集なら、今は問題集の間に差はそれほどありません。
いくら定評のある良い問題集をやっても、その問題集を1回しか復習しなかったら、ほとんど習得できません。宝の持ち腐れなのです。正しい勉強法をして、5回以上復習する。これを忘れないで下さい。
3.2.教材の選び方
(1)最重要な問題集は学校の教科書
数学が素晴らしくできる人を除いて、高校生は、まずは学校の教科書を完璧に解けるようにしましょう。人によって回数は違いますが、「問題を見たら即座に解き方が言える状態」にまで復習を繰り返します。平均で3~5回です。教科書はそれほど難しくないので、回数は受験用問題集より少なめです。解き方を即答できるようになった問題はどんどん外して、即答できない問題だけ復習を繰り返します。教科書がスラスラ解けるようになれば、基礎は大丈夫なので、受験用の問題集に入ることができます。
ちなみに、授業の予習と復習どちらが重要かというと、復習の方がずっと重要です。初見で解けるかどうかより、その問題が最終的に解けるようにすることの方が重要だからです。予習では、その問題が解けるかどうかだけ分かればOKです。よって、問題文を1~2分見て、解法を思いつけば解答を見て確認し、思いつかなければ解答を見て理解する、というくらいの軽い予習にします。1授業当たり15分以下というところでしょう。
授業で毎回ランダムに当てられて解答を黒板に書く必要のある場合でも、暗記数学を実践し、5分以上は考えず、分からなければすぐに解答解説を読んで理解し、また解きます。授業では、予習で分からなかった問題を真剣に聞き、理解し、家で復習します。分からなかった問題を3~5回復習し、「スラスラ解ける状態」にします。
(2)学校指定の問題集
テストに使われるなど、学校指定の問題集があるときは、教科書の次にそれを解いていきます。その問題集が簡単すぎるなど、自分の実力と合わないときに限り、別の問題集を自分で探して解いていきます。
(3)自分で定評ある良質の問題集を習得する①教科書が分からないとき
高校生の場合は時間があまりないので、学校と違う教材はできるだけ避けます。学校の教材をできるだけ有効活用して、それで足りないとき、時間に余裕があるときに、自分のレベルに合った問題集を使います。
教科書が分からないときは、まずは講義系問題集をやります。
「スバラシク面白いと評判の初めから始める数学」シリーズ(マセマ)
「沖田の数学1Aをはじめからていねいに」シリーズ(東進)
講義系問題集でも分からない場合は、下のレベルが分かっていないので、中学数学のやり直しをした方が良い場合が多い。まずは、中学数学レベルから復習しながら高校数学を教えてくれる以下のような問題集に取り組みます。
「とってもやさしい数学」の高校数学シリーズ(旺文社)
「やさしい高校数学」シリーズ(学研)
これで分からなければ、中学レベルからやり直します。
「やさしい中学数学」(学研)
「高校入試合格BON!数学」(学研教育出版)
「高校入試突破計算力トレーニング」(桐書房)
(4)自分で定評ある良質の問題集を習得する②学校教材が簡単な場合
逆に、学校の教材が簡単すぎる場合は、定評ある問題集を選んで、どんどん進めます。以下の教材は二次試験、私立大学入試の対策問題も含みます。
「スバラシク強くなると評判の元気が出る数学」シリーズ(マセマ)
「スバラシクよくわかると評判の 馬場敬之の合格!数学」(マセマ)
「理系対策数学12AB/3入試必携168」(数研出版)
「チャート式解法と演習数学(黄チャート)」シリーズ(数研出版)
「チャート式基礎からの数学(青チャート)」シリーズ(数研出版)
計算練習もやった方が良いでしょう。
「大学入試・共通テスト突破計算力トレーニング 上下」(桐書房)
(5)共通テスト対策:過去問問題集
教科書と標準的な問題集を習得し終わったら、過去問もしくは過去問を題材にした解説の詳しい問題集を解いていき、共通テストレベルの実力を培っていきます。
「スバラシク得点できると評判の快速!解答共通テスト数学」(マセマ)
「チャート式共通テスト対策数学1A+2B」(数研出版)
「文系・共通テスト対策数学12AB入試必携168」(数研出版)
「共通テスト 数学I・A よく出る過去問トレーニング」(中経出版)
「共通テスト 数学II・B よく出る過去問トレーニング」(中経出版)
「共通テスト過去問数学」(教学社)
4.終わりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
あなたの健闘を祈ります。
創賢塾のホームページに書かれた数学・英語等の勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
【口頭再現法で数学偏差値が上がっています】
Nさん(高校1年生、茨城県)
数学で、口頭再現法を教えていただいたことによって、難しい問題の解き方をその場で暗記することができるようになりました。
復習も、言われたとおり、毎週できるだけやるようにしたら、前回の河合塾模試で63を取ることができました。偏差値は今までより8くらい上がっています。ありがとうございます。
【第一志望の法政大学に合格できました】
Tさん(高校3年生、神奈川県、法政大学キャリアデザイン学部[偏差値60]合格)
第一志望の法政大学のキャリアデザイン学部(河合塾偏差値60)に合格することが出来ました。
教えていただく前は(河合塾)偏差値45~49前後でしたから、先生の授業がなければ、合格はなかったと思います。
全然解けなかった国語が、短い時間で要点を探して読めるようになり、学校のテストの偏差値も、模試の偏差値も10以上、上がりました。
毎回、先生に教えられたやり方で過去問の文章にキーワードとキーセンテンスに印を付けながら読み、授業でチェックしていただき、問題の解き方や内容を、徹底的に教えていたことで、読み方や解き方が身に付いたお蔭です。
英語も、先生に薦めて頂いた「入門英文解釈の技術70」「基礎英文解釈の技術100」がとても良かったです。英文解釈をやったお蔭で、英語長文への苦手意識が減り、分かる英文が飛躍的に増えました。英語が苦手なのでこれからも頑張っていきたいです。
数学も、先生に薦めて頂いたマセマの「初めから始める数学」「元気が出る数学」「合格数学」がとても良かったです。学校の「青チャート」よりずっと分かりやすく、進めやすかったです。それと口頭再現法で過去問が解けるようになりました。数学にして良かったです。
本当にありがとうございました!
【数学の成績が上がった】
Yさん(高校3年生、京都府)
3か月ほど前(2年生の1月)に、個別指導(駿台個別)の数学の先生に言われて共通試験の過去問の数学を解いてみました。結果、数学Ⅰ+A、Ⅱ+Bともに7割ほどでした。その先生は今の段階でこの点数が取れるのはなかなかいい調子だと言ってくれました。
ここまで数学の成績が上がったのは創賢塾で教えてもらった口頭再現法などの勉強法のおかげです。数学だけでなく、ほかの科目の成績も、例えば、
コミュ英語:15点(平均49点)⇒59点(平均48点)、
論理表現:16点(同49点)⇒62点(同48点)、
数学II:42点(同55点)⇒30点(同30点)、
数学B:25点(同58点)⇒49点(同53点)、
古典:35点(同64点)⇒77点(同67点)、
物理:15点(同40点)⇒46点(同29点)、
化学:43点(同62点)⇒95点(同70点)、
地理:27点(同61点)⇒50点(同63点)などに上がりました。
高校に入学してからの私は何を勉強してよいかわからず、成績も悪いままで、無気力になっていました。そんな私に勉強のやる気を起こさせてくれたのは創賢塾でした。だから、私にとって創賢塾との出会いはチャンスだと思います。
このような大事なチャンスを手に入れた以上は志望校合格に向け一生懸命努力していこうと思います。
【口頭再現法のおかげで数学で学年1位になりました】
Fさん(高校1年生、千葉県)
(新型コロナのために遅れて)6月には高校で初めての授業が始まり、テストが近くなったために、数学の口頭再現法を始めました。
実際に口で説明すると理解度が上がって、黙って解説を写していたときより自分の問題点(どこから分からなくなるかなど)が明確になってきました。
期末テストの結果は、数1:86点(平均72点)、数A97点(同65点)でした。口頭再現法をしっかりやった数学Aは学年1位でしたが、数学1に関しては口頭再現法をテスト直前にサボってしまい、数学Aほど良くありませんでした。先生の言う通りやるべきだったと反省しています。
夏休みの間、毎日、計算10分と口頭再現法4問を、きちんと実践していきます。