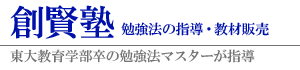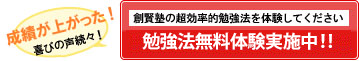高校生が定期テストの社会で90点以上を取るのは難しくありません。教科書を10~20回音読して理解し、一問一答問題集や穴埋めプリントで用語と用語の意味を暗記すればよいのです。可能なら、仕上げに問題集を10周します。
満点を取るつもりで、できることを全てやったら、90点以上は取れます。
教科書を丸暗記して高得点をとる方法もあります。それについては【高校生の定期テスト満点戦略(9-2)定期テストで教科書を丸暗記する方法】参照。
1.社会で高得点を取るためにすべき5項目
社会の定期テスト対策では、以下の(1)~(3)が必須で、(4)と(5)を追加すれば、より点数が上がります。
【社会で高得点を取るための5項目】
(1)用語の暗記:用語(人名・事件名・年号・地名等)を暗記しなければ点は取れないので、とにかく最初に用語を穴埋めプリントや一問一答問題集で暗記していきます。
「用語の暗記」とは、穴埋め問題や用語を問う問題で「大化の改新、ハンザ同盟、デカン高原」などと答えられるように、これらの用語を暗記する(言える、書けるようにする)ことです。
(2)用語の意味の暗記:用語の意味の暗記とは、「大化の改新=中大兄皇子と中臣鎌足が天皇中心の中央集権国家樹立を目指し、645年に、蘇我氏を滅ぼして始めた政治改革。646年に改新の詔が出された」など、用語の中身を自分で言える、書けるようにすることです。
用語だけ暗記しても、5~7割以上得点することは難しいでしょう(先生の問題の作り方によります)。よって、用語の意味を次に暗記していきます。
(3)内容の理解:用語と用語の意味だけを単独で覚えるだけでなく、教科書を何度も読むなどして、内容(因果関係、流れ)を理解すると、暗記もしやすく、点数も上がります。
例えば、日本史・世界史なら流れ(原因・理由と結果)の理解、地理なら気候・位置と農業・産業などの関係を理解すると暗記しやすくなります。
そのために、教科書のテスト範囲を、授業と並行して週3周、合計10周以上音読するなどし、内容を理解・暗記します。
(4)問題演習:時間があって高得点が取りたいなら、問題演習をするのがオススメです。
(5)テストの間違いの原因を特定し対策する:テストが返却されたら、「テストの間違いの原因を探し、対策を考え、ルーズリーフにまとめる」という作業をするのがオススメです。
ただやみくもに勉強するより、テストの形式に合わせ、自分の足りない部分を補う勉強をした方が、点数は上がりやすいからです。
2.用語暗記法
2.1.穴埋めプリントの暗記法
学校で穴埋めプリントが配られる場合、その用語と用語の意味を覚えれば平均点程度は取れる場合が多いので、用語は全部即答でき、書けるようにしておきます。ここではプリントが20問×20枚あるとします。
穴埋めプリントの暗記法
(1)1枚目1周目:テストしながら暗記:用語は赤シートで隠せるように赤やピンクペンで書きます。赤シートで隠し、地の文を理解しながら黙読し、用語を言います。覚えていない用語に印を付け、5回ほど音読していったん暗記します。1枚1周目が終わったらすぐ2周目に入ります。
(2)1枚を3~4周していったん即答できるようにする:2周目以降は地の文は全部読まず、印の付いた用語の前後を読んで答えを言います。正解なら次へ、不正解なら2つ目の印を付けて5回音読・暗記して次へ。
3周目は2周目に間違えた問題のみ解き、間違いがなくなるまで3~4周暗記し、全部暗記したら2枚目へ。時間の限り先へ進めます。
(3)テストまでに20周:テスト範囲(20枚など)を1周終わったらすぐに2周目に入り、同様の暗記法でテストまでに10~20周し、全部即答できるようにします。普通、15~20周したら完全に即答できるようになります。
(4)用語を書けるようにする:書けない可能性のある用語は、書いてテストし、書けなかった用語をルーズリーフにまとめ、【「テスト⇒書けない用語を5回前後書いて暗記」×7日】のように1~2日ではなく5~7日暗記します。
1~3日だと短期記憶にしか入っていないのでテストまでに忘れる可能性があるためです。
(5)復習:いったん完全に暗記してからテストまでに期間がある場合は、「週3回×30分」など復習をします。最初赤シートで隠しながらテストし、即答できない用語を音読で暗記します。
(6)理解のために教科書を10周音読する:用語だけ暗記しても高得点は期待できないので、教科書などをテストまでに10周ほど音読して、流れを理解し暗記します。理解した方が用語暗記もしやすくなるからです。
2.2.教科書で用語暗記する方法
教科書の用語を緑ペンで消して赤シートで覚えている人もいるでしょう。その時の暗記法を書きます。テスト範囲が40ページだとします。
教科書の用語暗記法
(1)1周目:テストしながら暗記:赤シートで隠し、地の文を理解しながら黙読し、用語を言います。覚えていない用語に印を付け、5回ほど音読していったん暗記します。見開き2ページが終わったらすぐ2周目に入ります。
(2)見開き2ページを3~4周していったん即答できるようにする:2周目以降は地の文は全部読まず、印の付いた用語の前後を読んで答えを言います。正解なら次へ、不正解なら2つ目の印を付けて5回音読・暗記して次へ。
3周目は2周目に間違えた問題のみ解き、間違いがなくなるまで3~4周暗記し、全部暗記したら次の見開き2ページへ。時間の限り先へ進めます。
(3)テストまでに20周:テスト範囲を1周終わったらすぐに2周目に入り、同様の暗記法でテストまでに10~20周し、全部即答できるようにします。普通、15~20周したら完全に即答できるようになります。
(4)用語を書けるようにする:書けない可能性のある用語は、書いてテストし、書けなかった用語をルーズリーフにまとめ、【「テスト⇒書けない用語を5回前後書いて暗記」×7日】のように1~2日ではなく5~7日暗記します。
1~3日だと短期記憶にしか入っていないのでテストまでに忘れる可能性があるためです。
(5)復習:いったん完全に暗記してからテストまでに期間がある場合は、「週3回×30分」など復習をします。最初赤シートで隠しながらテストし、即答できない用語を音読で暗記します。
(6)理解のために教科書を10周音読する:用語だけ暗記しても高得点は期待できないので、教科書をテストまでに10周ほど音読して、流れを理解し暗記します。理解した方が用語暗記もしやすくなるからです。
2.3.一問一答問題集の暗記法
用語は、一問一答問題集や穴埋め問題集を買って暗記しても良いでしょう。
ここでは「日本史B一問一答【完全版】」(東進)を例に、定期テストでの一問一答問題集の暗記法を書いていきます。テスト範囲が40ページだとして書きます。詳しくは【「東進 日本史B一問一答【完全版】」暗記法】参照。
【「日本史B一問一答【完全版】」暗記法】
(1)暗記:星3レベル(共通テストレベル)のみ暗記していきます。
(2)1周目:テストしながら暗記:右側の用語を赤シートで隠し、地の文を理解しながら黙読し、用語を言います。覚えていない用語に印を付け、5回ほど音読して暗記し、次へ。見開き2ページが終わったらすぐ2周目に入ります。
(3)見開き2ページを3~4周していったん即答できるようにする:2周目以降は地の文は全部読まず、印の付いた用語の前後を読んで答えを言います。正解なら次へ、不正解なら2つ目の印を付けて5回音読・暗記して次へ。
3周目は2周目に間違えた問題のみ解き、間違いがなくなるまで3~4周暗記し、全部暗記したら次の見開き2ページへ。時間の限り先へ進めます。
(4)テストまでに20周:テスト範囲を1周終わったらすぐに2周目に入り、同様の暗記法でテストまでに10~20周し、全部即答できるようにします。普通、15~20周したら完全に即答できるようになります。
(5)用語を書けるようにする:同上。
(6)復習:同上。
(6)理解のために教科書を10周音読する:同上。
【創賢塾の勉強法で日本史は学年3位でした】
Fさん(高校1年生、千葉県)
期末テストの結果が返ってきました。
先生に教えていただいた通りに勉強した科目に関しては、90点以上またはトップ3に入ることが出来ました。
点数は、コミュニケーション英語97点(同75点)、論理表現91点(同76点:学年2位)、数学A97点(同65点:学年1位)、現代文84点(平均69点:学年2位)、古文92点(同78点)、世界史91点(同86点)、日本史97点(同87点:学年3位)でした。
しかし、少しサボった科目-数学1:86点(平均72点)、生物基礎83点(平均77点)、化学基礎87点(平均72点)-に関しては満足いかない点数でした。総合では学年4位でした。
反省点がたくさんあるので、夏休みも、教えていただいた、英語の瞬間英作文、音読法、数学の口頭再現法、古文単語の暗記法、訳の暗記、品詞分解などをしっかり続けていきます。
英単語の暗記(クイック・レスポンス法)は、出来るだけ毎日2時間やっているのですが、とても効果があり、実際に実践できた日はその日の英単語はほとんど覚えることが出来ています。これからも続けていきたいです。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
3.用語の意味の暗記法
【「用語の意味」の暗記法】
(1)「テストの間違いの原因探しと対策」でどういう用語の意味が問われたかを把握する:教科書の太字、欄外、学校のプリント、授業で強調した用語、資料集など、先生によって出典が異なるので、まずはテストの傾向を調べ、それに応じた対策を取ります。
(2)出やすい種類の用語の意味をルーズリーフにまとめる:例えば、用語の意味が問われるのが、主に、十字軍、第一次世界大戦、大化の改新など、重大事件・重要事項の場合(たいていそうですが)、重大事件・重要事項を以下のようにルーズリーフに一問一答式でまとめます。
【7世紀中頃の政治改革と人・目的・年号・政変・内容は?|大化の改新。中大兄皇子と中臣鎌足(中心的な人)が天皇中心の中央集権国家樹立を目指し(目的)、645年(時代・年号)に、蘇我氏を滅ぼして(政変・戦争)始めた政治改革。646年に改新の詔(改革の内容)が出された】
まとめるのは、歴史科目の場合、「いつ、誰が、何を原因とし、何をして、どういう経過をたどり、どういう結果になり、その後の影響は何か」など。それを、教科書・プリント・用語集などを参考に自分でルーズリーフにまとめます。
1つの定期テストでは、テスト範囲はだいたい40ページ前後で、1ページに重要事項は2個前後ですから、約80項目をまとめればよいでしょう。自分でまとめたら半分暗記できるので、暗記するのは簡単です。
(3)まとめのルーズリーフの暗記法:右側を紙で隠し、右の内容を言い、紙をずらして右を見て、覚えていない内容があれば5~10回くらい音読して暗記し、1ページ終わらせます。そのページをあと2周前後行い、いったん全部即答できるようにします。
そのまま2ページ目、3ページ目と進め、テストまでに全体を10~20周して全部即答できるように暗記します。
4.流れの理解
流れの理解については、学校で教科書を使っている場合は、毎週、テスト範囲を3回以上音読し、理解します。
受験勉強を始めている人は、教科書より分かりやすい参考書でも構いません。日本史であれば以下のような参考書です。これも、毎週テスト範囲を3回音読し、理解します。
「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(語学春秋社)
「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」(ナガセ)
「これならわかる!ナビゲーター日本史B」(山川出版社)
【創賢塾の勉強法で、テストの点数が21点上がりました】
Mさん(高校2年生、東京都)
私立文科系志望で選択科目は日本史です。高校2年生までは英語を主体に勉強をしてきました。
社会の選択科目は日本史で、やることはやっていましたがただ単純に一問一答を暗記するだけでした。この方法では学校の定期試験も60点台で頭打ちの状態でした。
創賢塾を受講するようになり、先生から最初に教えていただいた勉強方法はまず日本史流れを徹底的に理解しなさいということでした。具体的には「日本史石川の実況中継」を範囲を決め5回黙読すること、そしてその範囲の一問一答を20周暗記するということでした。
実況中継を一周するときは少し苦労しましたが、2周めはそれほど大変でもありませんでした。そして2周した後からは一問一答の暗記の定着率がとても上がりました。最終的に5周した時には以前の方法に比べると格段に暗記の定着率が上がったと実感しました。
最近期末試験が終わったのですが、日本史のテスト結果は82点でした(前回から21点アップ)。やはり創賢塾の勉強方法はすごいと実感しました。
5.問題演習
問題演習をする時間的余裕のある人はあまりいないでしょうが、受験科目に決めていて、高得点を取りたい科目は以下のような共通テスト用問題集を解いた方が点数は上がりやすくなります。
「ベストセレクション 共通テスト 世界史B重要問題集」「同 日本史B」(実教出版)
「共通テストへの道 世界史」「同 日本史」「同 地理」(山川出版社)
「短期攻略共通テスト 世界史B」「同 日本史B」「同 地理B」(駿台)
「スピードマスター世界史問題集」「同 日本史B」「同 地理B」(山川出版社)
【地理の点数が27点⇒50点に上がった】
Yさん(高校3年生、京都府)
3か月ほど前(2年生の1月)に、個別指導(駿台個別)の数学の先生に言われて共通試験の過去問の数学を解いてみました。結果、数学Ⅰ+A、Ⅱ+Bともに7割ほどでした。その先生は今の段階でこの点数が取れるのはなかなかいい調子だと言ってくれました。
ここまで数学の成績が上がったのは創賢塾で教えてもらった口頭再現法などの勉強法のおかげです。数学だけでなく、ほかの科目の成績も、例えば、
コミュ英語:15点(平均49点)⇒59点(平均48点)、
論理表現:16点(同49点)⇒62点(同48点)、
数学II:42点(同55点)⇒30点(同30点)、
数学B:25点(同58点)⇒49点(同53点)、
古典:35点(同64点)⇒77点(同67点)、
物理:15点(同40点)⇒46点(同29点)、
化学:43点(同62点)⇒95点(同70点)、
地理:27点(同61点)⇒50点(同63点)などに上がりました。
高校に入学してからの私は何を勉強してよいかわからず、成績も悪いままで、無気力になっていました。そんな私に勉強のやる気を起こさせてくれたのは創賢塾でした。だから、私にとって創賢塾との出会いはチャンスだと思います。
このような大事なチャンスを手に入れた以上は志望校合格に向け一生懸命努力していこうと思います。
6.テストの間違いの原因と対策
6.1.テストの間違いの原因を特定し、対策する
創賢塾では、テスト後すぐに、英数と点数が悪かった科目について、「テストの間違いの原因を探し、対策を考え、ルーズリーフにまとめる」という作業をしてもらいます。
ただやみくもに勉強するより、テストの形式に合わせ、自分の足りない部分を補う勉強をした方が、点数は上がりやすいからです。
例えば、穴埋め用語問題は90%正解で、用語の意味を問う問題で30点中20点落とし、記述問題で25点中20点落としている場合は、用語暗記はうまくいっているので同じ勉強法でOKで、用語の意味と記述問題用の勉強を強化する必要がある、ということが分かり、次回のテストではそれに合わせて勉強をします。
これをすることの重要性は誰でも分かると思いますが、しかし、実際にやっている人はほとんどいません。面倒だからです(^.^; 。よって、これをやれば成績は上がります。
6.2.具体的やり方
「テストの間違いの原因探しと対策」は、具体的には以下のようにします。
【テストの間違いの原因探しと対策】
(1)原因を書く:テストの問題用紙の間違えた問題に印を付け、テスト用紙の右端に、間違えた問題の原因をできるだけ詳しく書いていきます。用語の暗記なのか、漢字の綴りなのか、用語の意味なのか、流れ・理解不足なのかを書きます。
(2)間違えた問題について、学校のプリント・教科書の、どういう箇所を暗記すべきだったかを探る:例えば、間違いの90%が教科書の太字なら、太字や太字の意味を暗記すればよいと分かります。教科書の欄外が結構出ているなら、そこも暗記すべきだと分かります。
記述問題が全て、大事件・重要事項・先生が強調した箇所についてなら、それらの内容を暗記すべきだと分かります。
(3)原因のまとめと対策をルーズリーフに書く:以上の分析のまとめと、そこから分かる対策を以下のように書きます。
【2年1学期期末テスト・日本史|原因:用語10個中2個-4点(共に教科書太字)、用語の意味15個中10個ー20点(欄外2つ、あとは太字の意味の暗記で全部取れた)、記述3問25点中-20点(大事件、太字の意味の暗記で全部取れた)。
対策:プリントの用語暗記徹底、大事件・先生が強調した内容・太字の用語の意味をまとめて暗記。】
(4)毎回書く:以上を毎回のテスト・模試でやっていくと、ルーズリーフのまとめを見たら、どこまで暗記したらいいか、どういう勉強をしたら成績が上がるかの対策が分かります。
7.最後に
社会は暗記が9割!なので、暗記すれば簡単に高得点が取れます。
ただし、暗記の仕方にもコツがあります。以上に簡単に暗記法も書きましたが、そのほかにも多数の暗記法があります。暗記が苦手な場合、創賢塾にお問い合わせ下さい。生徒には全てお教えしています。
あなたの健闘を祈ります。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
【定期テストの成績が上がっています】
Mさん(高校3年生、静岡県)
5月に行われた中間テストの結果が返ってきました。論理表現が25点、現代文が18点、化学が19点、生物が49点、地理が10点上がっていました。偏差値では特に化学と地理が10、生物は15上がりました。
論理表現では例文暗記の方法、現代文では10分音読などのテスト勉強法、理社の暗記法・問題集の習得法が役立ちました。ありがとうございます。
来月上旬に行われる期末テストでは今回の結果の反省を生かし、点数を更に上に伸ばしたいです。
■2年3学期末テスト(教わる前):英表28点(平均35点)、現代文51(49)、化学18(50)、生物13(38)、地理B51(63)
■3年1学期中間テスト:英表53点(平均50点)、現代文69(63)、化学37(47)、生物62(61),地理B61(64)
【社会の暗記は音読が有効】
Nさん(高校1年生、茨城県)
社会(世界史、現代社会)のテスト勉強対策で、先生に音読をすすめられてやってみたところ、想像以上に覚えられました。
特に、世界史の人物の聞いたこともないようなカタカナの名前などは、音読することで楽に覚えられました。もう音読以外の方法で世界史の人物名を覚えることはできないと思いました。
【高校生の定期テスト満点戦略(メニュー)】
(1)全体方針編
(2)定期テストで入試対策編
(3-1)コミュ英語
(3-2)論理表現
(3-3)英語読解力
(4)数学
(5-1)現代文①定期テスト対策編
(5-2)現代文②読解力編
(5-3)現代文③論理的読解力編
(5-4)現代文④論理的記述力編
(5-5)現代文⑤小論文編
(5-6)現代文⑥論理的解答力編
(5-7)現代文⑦真の理由と対策編
(6)古文
(7)漢文
(8)理科
(9)社会