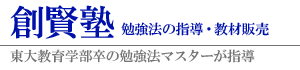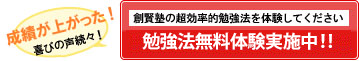受験勉強は2つの時期に分かれます。入試基礎力養成期と入試合格力養成期です。
このページでは、古文の大学受験における入試合格力養成期の勉強法について書いていきます。
具体的には、高校生が、入試基礎力を養成した後、塾に頼らず、できるだけ自力で、どういう教材を、どう勉強して、古文を合格レベルまで持っていくかを書きます。
1.受験勉強の2つの時期
1.1.入試基礎力養成期
入試基礎力養成期の教材・順序・勉強法は【受験勉強(2)入試基礎力養成期の勉強法】に詳しく書いています。
1.2.入試合格力養成期
この時期には、「志望校に合格するレベルの古文力」、言い換えれば、「共通テストで8~9割以上、難関大学~超難関大学(偏差値65~70以上)の過去問でも合格点(7割以上)を取れる古文力」を培います。偏差値で言えば70以上を目指します。
※偏差値:このホームページで”偏差値”という場合、河合塾偏差値を指します。同じ偏差値でも業者によってレベルが違うので、標準的な河合塾偏差値で考えます。
※志望校偏差値が60~65以下の場合、入試基礎力養成期の勉強をしっかりやれば、それだけで多くの受験生が合格レベルに到達します。
入試合格力養成期に使う教材は、以下の通りです。
【入試合格力養成期の教材の全リストとその使用順序】
(1)過去問:3年8月以降のメイン教材は志望校過去問です。過去問を10年分以上解き、習得して、志望校レベルの実力を身に付けていきます。
(2)弱点補強問題集:過去問を解いて分かった自分の弱点を補強するため、古文単語帳、古典文法問題集、「読み方・解き方本」、記述問題集、和歌本、古文常識本、文学史本などを、必要に応じて、習得します。
これについては【受験(4)過去問弱点対策法】に書いています。
(3)志望校・共通テスト対策のための教材:必要に応じて:個別大学専用問題集を解いたり、スタディサプリの共通テスト対策動画等を見て、専門家の解き方を参考にすることは、あなたの合格力を強化します。
これについては【受験(5)共通テスト古文対策法】に書いています。
2.過去問を解く前提
2.1.過去問を解き始める時期
以下の受験生は、過去問を中心に解いていきます。
(1)偏差値突破:入試基礎力養成期の教材を暗記し、「品詞分解+現代語訳の暗記」を30~50ページ以上習得して、古文偏差値が志望校レベルを超えた3年生、もしくは偏差値が65以上になった3年生。
(2)通常は3年夏休み頃から:上記を習得できなくても、夏休みになった3年生は過去問を解き始めます。
2.2.過去問を早々に解いた方が良い理由
過去問は、高3の夏休み頃から解いた方が良いです。その理由は以下。
(1)対策には時間がかかるから:過去問の傾向や自分の間違いの傾向によって、その後の勉強内容・教材を変えたり追加したりする必要があり、対策にはそれなりに時間がかかります。
例えば、自分の間違いが、文法力に問題があるのか、単語か、古文常識か、記述力かによって、勉強内容を変える必要があります。
(2)過去問を解くのは時間がかかるから:過去問を「週1年分×10年分」解き、習得するだけでも数ヶ月かかります。
【夏休みから過去問に取り組むことで効率よく勉強できる】
Sさん(高校2年生、東京都)
夏休みから大学の過去問を解き始めることをこの授業で勧められました。
私は中学生の頃、塾に通って受験対策をしていましたが、過去問を解き始めたのは12月でした。そのため自分の弱点に気付くのが遅くなってしまい、全て克服できませんでした。
しかし今回、夏から取り組むことで早く弱点に気付き、今苦手克服のため効率よく勉強できています。また傾向や感想などをメモすることで各大学に応じた対策を練ることができます。
今後も様々な問題を解いて、受験までの時間を上手に使っていきたいです。
2.3.過去問が重要な理由
過去問は、「自分が受験するときの問題に傾向が最も似ている問題集」だから、重要なのです。
※過去問の傾向とは:和歌の有り無し、古文や問題の難易度、語彙問題・選択肢問題・記述問題等の問題の種類等。
市販の問題集は、過去問と傾向が似ているとは全然限らないので、過去問を解く実力がある受験生が、市販の普通の問題集を、過去問より優先的に解く理由はありません。
2.4.過去問を集める(1)共通テストを受ける場合
「共通テスト 赤本」と共通テスト用問題集を買います。
できるだけ、最初に、共通テスト用の「読み方・解き方本」である「共通テスト古文 満点のコツ」を習得し、その後、共通テスト過去問、共通テスト用問題集の順に解いていきます。
「共通テスト古文 満点のコツ」(教学社)
「共通テスト 赤本」(教学社)
「共通テスト実戦模試(5)国語」(Z会)
「共通テスト総合問題集 国語」(河合塾)
「共通テスト実戦問題集 国語」(駿台)
「共通テスト 古文・漢文 実戦対策問題集」(旺文社)
2.5.過去問を集める(2)二次に古文がある国公立大学が第一志望の場合
第一志望の国公立大学の過去問を10年分以上、受験する私立大学の過去問を各5年分以上集めます。
8~10月は共通テスト・国公立大学の過去問を中心に解き、11月以降、私立大学過去問も少しずつ入れていきます。
2.6.過去問を集める(3)古文がある私立大学が第一志望の場合
受験する私立大学の過去問を各5~10年分以上集め、週1つなど解いていきます。
2.7.過去問の選択
(1)共通テストを受ける受験生
入試基礎力養成期の教材を習得し、「品詞分解+現代語訳の暗記」を30~50ページ以上終えていれば、共通テスト過去問も結構解けるはずなので、【「共通テスト古文 満点のコツ」⇒共通テスト過去問】の順で問題演習に入ります。
二次に古文がある国公立大学受験生の場合、その後、二次の過去問を解きます。
共通テストを受ける中堅以下(偏差値60以下)の私立大学志望者は、【「共通テスト古文 満点のコツ」⇒共通テスト過去問+志望大学過去問】の順で解きます。
共通テストを受ける(偏差値60以上の)難関私立大学志望者は、【「共通テスト古文 満点のコツ」⇒共通テスト過去問⇒志望大学過去問】の順で解きます。
(2)共通テストを受けない私立大志望者
中堅以下の私立大学志望者は、【「読み方・解き方本」⇒志望大学過去問】の順で解きます。
難関私立大学志望者は、【「読み方・解き方本」⇒共通テスト過去問+中堅私立大学用問題集⇒志望大学過去問】の順で解きます。いきなり難しい難関大過去問を解く前に、共通テスト過去問のようなミドルレベルの問題を10~20問解き、習得してから難関大過去問に入るのが得策です。
「読み方・解き方本」の選択肢は以下です。オススメは「山村由美子 図解古文読解講義の実況中継」(全受験生向け)、「共通テスト古文 満点のコツ」(共通テストを受ける受験生向け)、「古文解釈の方法」(上級者向け)です。
「山村由美子 図解古文読解講義の実況中継」(語学春秋社)
「古文解釈 はじめの一歩」「古文解釈の方法」(関谷浩著、駿台)
「共通テスト古文 満点のコツ」(教学社)
「元井太郎の古文読解が面白いほどできる本」(中経出版)
「岡本梨奈の古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本」(角川)
「ライジング古文」(桐原書店)
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
3.過去問の解き方と習得法
3.1.過去問の解き方
【古文の過去問の解き方と習得法】
(1)過去問を解く
①制限時間で解く⇒延長して解く:まず、制限時間で解きます。時間内に終わらなかったら、10~20分など延長して解きます。解かないのはもったいないからです。
そして、両方、分けて点数化できるように印を付けておきます。時間内の点数が「本番であれば何点取れるか」で、延長の点数は「今の実力でどこまで解けるか」を示します。
②読み方:リード文(最初の人物・背景説明)や注もしっかり読み、登場人物を丸で囲み、敬語や助詞などをヒントに主語を確定しながら読みます。
読んでいて傍線部問題や穴埋め問題があれば、その都度問題を読み、前後を読んで解いていきます。
③解き方:傍線部問題では、傍線部について、欠けている要素(主語・述語・目的語等)を補い、指示語があれば指示内容を明らかにし、会話文に「」を付け、(必要に応じて)品詞分解をして、できるだけ正確に傍線部を現代語訳し、また、前後の文(文脈)にも注意を払い、理解します。
選択肢問題の場合、傍線部やその前後の意味がよく分からなくても、選択肢(≒正解肢は一種の現代語訳)をヒントに本文と照らし合わせて解きます。
このあたりの読み方・解き方は「山村由美子 図解古文読解講義の実況中継」「共通テスト古文 満点のコツ」などの「読み方・解き方本」に詳しく書かれています。過去問を読み、解くときには「読み方・解き方本」のテクニックを用い、習熟していきます。
④理解できない箇所に印:読んでいて意味が分からない単語・箇所・文や、主語が分からない述語に印を付けておきます(復習のため)。
(2)自己採点する
①自己採点:解き終わったら解答解説・現代語訳を読み、自己採点します。
②問題を間違えた原因・理由を理解する:間違えた問題に印を付け、なぜその解答になるのか、自分の答えではなぜダメなのかをしっかり理解します。
知識(単語・古文常識等)が原因なら、ルーズリーフにまとめ、暗記し、文法(助動詞・助詞等)が原因なら品詞分解をし(自分で分からなければ学校の先生などに聞きます)、5~10回復習して習得します。
後日、同じ問題を解いても、正しい根拠で正解が導けるように、きちんと理解し暗記します。
(3)過去問まとめ帳を書く
①過去問まとめ帳:過去問を自己採点したらすぐに、過去問の傾向・自分の間違いの傾向・今後の対策を、以下のように、ルーズリーフに「過去問まとめ帳」を書きます。「過去問まとめ帳」は過去問の全科目で作ります。
【共通テスト21年、古文 傾向|「栄華物語」、問5に和歌の現代語解説(+和歌)がある、文章・問題とも難しめ。8問中3問不正解(原因:古文単語1、主語の確定+内容理解2)、分からない古文単語10個、問題に関連して分からない品詞分解2】
【 〃 〃 対策|和歌の解釈ができない⇒和歌の基礎知識を暗記、和歌の問題を共通テスト過去問等で解く、単語力不足⇒単語帳復習、「品詞分解+現代語訳の暗記」⇒過去問を週1問、共通テスト用問題形式に慣れる必要がある⇒共通テスト用問題集を2週に1問解く】
②過去問の傾向とは:作品名・時代、和歌の有り無し、難易度、語彙問題・選択肢問題・記述問題等の問題の種類等。
③自分の間違いの傾向:点数、どういう問題で間違えたか、意味が分からなくなった原因or間違えた原因(和歌の読み取り・単語・助動詞・品詞分解・古文常識)等。
(4)過去問を習得する
①習得する:過去問は解きっぱなしではなく、習得します。習得とは以下の4つを指します。
②習得1:「品詞分解+現代語訳の暗記」:【古文・品詞分解を12時間で習得する方法】を参照。
③習得2:暗記:問題に関わる、知らない知識(単語・古文常識など)を全部暗記ルーズリーフにまとめ、暗記します。
④習得3:長期記憶に入れる:上記の習得後、その復習を2ヶ月以上続け、長期記憶(数ヶ月~数年以上もつ記憶)に入れていきます。詳しくは、【初見の古文をスラスラ訳せるようにする勉強法】。
⑤習得4:3回以上解く:何度も解くことで、入試問題の読み方、解き方に慣れていきます。特に、記述問題は、何度も書くことで、記述力が上がります。
2回目以降に解くときは、どこで・なぜ文の意味が分からなくなるか-主語か敬語か助動詞かなど-を調べながら読みます。
問題が解けない・間違えた場合は、解いた後で、何が原因で問題が解けないかを考え、原因に当たる本文に印を付け、それを解決する勉強(品詞分解・単語の暗記等)をします。
3.2.「品詞分解+現代語訳の暗記」
過去問の学習と並行して、過去問・「読み方・解き方本」・(品詞分解用の)「理解しやすい古文」(文英堂)等で、「品詞分解+現代語訳の暗記」を毎週合計1ページ以上進め、その復習も毎日1ページなど行っていきます。
過去問学習を始めてからは、過去問を中心に「品詞分解+現代語訳の暗記」をします。
4.過去問について
4.1.一年分全体を解くか、大問ごとに解いても良いのか。
過去問は、国語1年分を全体で解いた方がもちろん良いですが、時間もかかりますし、それぞれの科目(現代文・古文・漢文)の進み具合も違うので、必ずしも全体を一気に解く必要はありません。
ただ、時間管理を学ぶため、10月以降、1ヶ月に1回くらいは国語1年分を全問、時間通り解くのがオススメです。
※時間管理:最後まで到達し、解ける問題を全部解き、全体の点数を最大化するため、どういう順番で解くか、各大問に何分かけるか、解けない小問を最大何分くらい考えるか、などを検討し、決めていくこと。
4.2.過去問に関する誤解
「過去問の問題文(古文)は二度とその入試に出ないのだから、解くのは無駄だ」と考える受験生がいます。
しかし、それは間違いです。
なぜなら、同じ問題文が出る確率は、過去問(ほぼ0%)と他の問題集(ほぼ0%)でほとんど差は無いからです。
ですから、問題文や問いの傾向が「自分が受験するときの志望校の問題」に最も似ている過去問を重視するのは当然です。
4.3.過去問を習得すべき理由
過去問の古文を習得しようとする受験生はほとんどいませんが、創賢塾では、過去問を【5年分⇒10年分⇒20年分】習得してもらいます。
その理由は以下の通りです。
(1)習得すれば古文読解力が上がるから。
過去問の古文を、週1ページ分、「品詞分解できて(=文法的に完全に理解できて)、意味が理解できる」ようにし、また、問題に関わる重要な知識(単語・古文常識など)を暗記すればするほど、初見の古文(過去問・実際の入試問題・模試の古文)を読んだとき、文法的に理解できる割合が増え、意味が分かる箇所・古文単語数も増えます。そうすれば、過去問の得点率も上がるのです。
言い換えれば、過去問を次々解いても、習得をしなければ、古文読解力はたいして上がりません。
(2)過去問に合わせた勉強ができるから。
過去問を何回も解いたり、「品詞分解+現代語訳の暗記」をすることで、過去問の古文・単語・設問の難易度・レベルが体感として分かり、対策を立てやすくなります。
例えば、現代語訳の記述問題が出て、自分が苦手な場合、「読み方・解き方本」の記述問題対策箇所や記述問題集を読み、何度も解くことで、どうやって現代語訳すれば良いかが分かってきます。
5.最後に
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
志望校に合格するには、長期記憶に入れる勉強法を実践し、過去問を問題集として解きまくることが役立ちます。
合格したかったら、過去問をガンガン解き、習得しましょう。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
「4ヶ月で古文偏差値が50から63になった」
Aさん、高校2年、三重県
お世話になっています。今回は古文について書かせていただきます。
古文は模試でいつも偏差値50くらいで、良くも悪くもなかったのですが、夏休み前に古文を上げたいと先生に相談すると、「品詞分解と現代語訳の暗記がいいよ」というお返事でした。さっそく「理解しやすい古文」で毎日1時間、品詞分解と現代語訳の暗記を始めました。
最初は慣れていなかったので1時間やってもなかなか進みませんでしたが、4~5日同じ箇所を続けるとさすがに慣れてきて、スラスラ言えるようになっていました。気を良くして一つ一つ追加していき、夏休み中に10文の品詞分解と現代語訳の暗記がスラスラできるようになりました。その後も平日30分、土日に1時間ほど続け、11月には30文が終わりました。
11月の模試では古文偏差値63を取ることが出来ました。以降も63~65くらい取れています。古文の勉強法が分かり、足を引っ張らなくなりました。ありがとうございました。