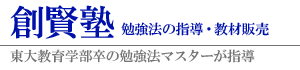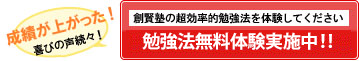このページでは、定期テストの時に、テスト範囲の教科書を丸暗記する方法を、日本史教科書を例に、書いていきます。この暗記法は、世界史などでも基本的に同じように使えます。
1回の定期テストの範囲は40ページ前後なので、ここでは40ページを丸暗記する方法を解説します。30ページでも60ページでも、暗記法は基本的に同じです。
この方法で40ページを暗記できれば、あとは時間をかけるだけで、教科書1冊分も暗記できます。つまり、40ページ暗記を成功させれば、定期テストだけでなく、模試でも入試でも日本史の成績を爆上げできるということです。
まずは40ページで試してみて下さい。
1.10ページを丸暗記してみる
1.1.丸暗記10ページからトライ
最初から40ページを丸暗記しようとするのは、時間も労力もかかり、なかなか覚えられないので、まず10ページくらいでやってみるのがオススメです。10ページだと簡単に覚えられ、また、10ページが可能なら40ページでも可能だと自信が持てるからです。
やることは、テスト範囲の10ページを、9割以上暗記できるまで、10~20周前後音読するだけです。
10周音読すれば誰でも3~9割暗記できます。平均5割です。5割でも暗記できれば、あとは周回数の問題で、15周読めば7割、20周読めば9割以上暗記できます。
9割暗記できたら、あとは週1周黙読で復習するだけで、テストまで記憶を維持できます。
そして、10ページ丸暗記に成功したら、残りの30ページを丸暗記します。
「部屋中歩き回って音読し、社会の教科書2冊を丸暗記した」
ブログ「音読のすすめ」より
”音読”、まさに合理的な勉強方法です。私も若いとき自分の部屋で眠くならないために本を持って声を出して読んで部屋中歩き回った思い出があります。こうすると頭の中にしっかり入って眠気防止の一石二鳥。
中3の受験のときはこれで社会の教科書2冊を丸暗記しました。
1.2.「9割暗記」とは
9割暗記とは、以下の書き込み教科書や共通テストレベルの穴埋め問題集・一問一答問題集で9割以上の用語とその意味を言えて、歴史の流れを説明できる状態です。
※書き込み教科書:教科書の文章をそのまま使い、太字(重要語)を穴埋めにした教材。
※歴史の流れとは:政治・経済・文化等の特定のテーマに関する「時代背景・因果関係(原因と結果)・主要人物・経過・後代への影響」などのことです。
「書きこみ教科書 詳説日本史」(山川出版社)
「時代と流れで覚える! 日本史B用語」(165ページ、文英堂)
「最速で覚える日本史用語」(207ページ、学研プラス)
「瞬間記憶! つなげて覚える日本史B用語」(224ページ、かんき出版)
「スピードマスター日本史問題集」(122ページ、山川出版社)
「共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる一問一答」(角川)
「共通テスト 日本史B一問一答【完全版】」(東進)
「山川 一問一答日本史」(山川出版社)
「一問一答 日本史Bターゲット4000」(石川晶康著、旺文社)
「入試に出る 日本史B 一問一答」(Z会)
「日本史B一問一答【必修版】」(東進)
1.3.教科書丸暗記のメリット
教科書10ページの丸暗記を1度成功させたら、あなたの人生が変わります。
効率的な暗記法を身に付けることで受験で有利になるからであり、また、「教科書10ページの丸暗記なんて自分にできるわけがない」という、自分の能力を制限していたリミッター(限界=固定観念)が外れ、「自分にもできる」という自信が生まれるからです。
1.4.音読か黙読か
当塾では、教科書暗記には、黙読より音読を推奨しています。
理由は、音読であれば、(10~20周必要ですが)ほぼ誰でも確実に暗記できるためです。
黙読の場合、5~10周で暗記できるスゴイ人もいる一方、40~50周読んでも暗記できない人もいます。集中力が足りない、きちんと理解していない、などの理由だと思いますが、それを変えるのは難しいので、回数を読めば確実に暗記できる音読の方がオススメです。
ただし、音読できない場所で読むときや、疲れているときなどは黙読でも構いません。その際、黙読1周は0.5周でカウントします。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
2.教科書丸暗記法
2.1.暗記法
ここでは、定期テスト1ヶ月前から、テスト範囲40ページのうちの10ページ分を1週間ほどでまず丸暗記し、次いで残りの30ページを2週間ほどで丸暗記する方法を書いていきます。
【定期テストで日本史教科書40ページを丸暗記する方法】
(1)10ページ暗記する
①暗記法:教科書のテスト範囲の10ページの本文を、「平日10ページ(1周15分)×1日2周(30分)×5日=10周、土日1周15分×5周(1日75分)×2日=10周」など、1週間前後で合計20周ほど音読します。
これだけで、たいていの人は9割以上暗記できます。もし20周で9割暗記できなくても、回数を増やせば9割暗記できます。
②最初は本文のみ音読する:欄外や史料、写真や絵の解説は、10周目までは、理解のために1回だけ音読します(1周目でも10周目でも可)。
表・系図・地図・写真・絵などは、本文と関係しているときにチラッと見るくらいにします。負担を軽くするためです。
11周目から(本文を半分以上暗記した頃から)、欄外等も毎回音読し、系図等も毎回しっかり見て理解します。ただ、記憶力に自信がある人は最初から全部音読しても構いません。
③用語集等を併用する:教科書を読んでいて、理解できない箇所、知らない人物・用語などがあったら、用語集・参考書・資料集等で少しずつ調べ、欄外にメモしておきます。
④丸暗記できるまでの音読回数と日にち:何周で暗記できるかは個人によりますが、10~20周前後音読すれば、ほとんどの人が9割以上暗記できます。20周でいまいちなら、回数を増やします。
テスト4週間前から暗記を始め、10ページを1週間で、残り30ページを2週間で暗記すれば、テスト1週間前には暗記が終わる計算になります。できればこのように余裕を持って暗記したいところです。
⑤メモする:何周で暗記できるかは個人によりほぼ一定ですから、何周で暗記できたか、何時間かかったかをメモしておきます。そうすれば、次の範囲、次のテスト、受験勉強で、回数、時間、日数の予想ができます。
(2)暗記チェック1:問題集を解く
①問題集を解く:10~20周ほど音読して、9割暗記できたと思ったら、上記の「書きこみ教科書 詳説日本史」等の問題集を解いてみます。
これは、暗記のチェックと強化をするためです。
②解き方:1~2日で教科書10ページ分の該当箇所を全て解き、間違えた穴埋め部分(重要語)を暗記します。
具体的には、地の文を黙読し、穴埋め箇所を言い、解答で確認し、間違えた箇所に印を付け、5回ほど正解を音読していったん暗記し、次へ。10ページ分終わったら、その日から、全て即答できるようになるまで、印の箇所を1日3周ほど暗記します。
穴埋め部分を全部即答できるようにして、余裕があれば、以下の暗記チェック2を行います。
(3)暗記チェック2:キーワードのチェック
①キーワードとその意味を言う:教科書の、1ページに1つほどの小見出しを見て、その項目の文章中にある太字のキーワードとその意味(人物の業績、戦争の流れ等)を全部言い、本文でチェックします。
例えば、「奥州藤原氏:11世紀末から、清衡・基衡・秀衡の3代100年にわたって、金や馬などの産物の富で京都文化を移入し、北方の地との交易によって独自の文化を育て、中尊寺などの豪華な寺院を建立し、繁栄を誇った」などです。
②暗記:言えなかったキーワードとその意味を丸で囲むなどし、5~10回音読していったん暗記します。そして、音読時に、より注意して読みます。キーワードとその意味を9割以上言えるようにしたら、次の30ページへ進みます。
(4)残りの30ページを暗記する
①暗記法:教科書のテスト範囲の残りの30ページを15ページずつ、【「平日15ページ(1周23分)×1日2周×5日=10周、土日4周(92分)×2日=8周(週18周)」】など、1週間で合計20周ほど音読し暗記します。
あとの暗記法は10ページの時と同じです。
②ページ数:残りの30ページを一括して暗記しても良いし、「15ページ×2セット」にしても構いません。自分の意欲・勉強時間・テストまでの期間等を考慮して決めます。
③復習:15ページの新規部分を暗記する一方、既習10ページは週1周黙読で復習します。そうするだけで、通常はテストまで記憶を維持できます。
④チェック:1周の黙読で維持できるかどうかには個人差がありますから、問題集を週1回復習し、キーワードとその意味のチェックを週1回行って、忘却具合をチェックします。
それで特に問題なければそれをテストまで続け、忘却していっているのが分かったら、黙読回数を増やしたり、音読に切り替えて、忘却を防ぎます。
⑤40ページの復習:40ページの丸暗記が終わって、まだテストまで期間がある場合、先の10ページと同じく、黙読や音読で復習します。
2.2.用語集・参考書を併用する
理解のために、以下のような用語集・参考書・資料集を1冊ずつ用意し、分からない用語・解説があったときなど、随時調べます。
「日本史用語集」(山川出版社)
「日本史用語集〈究〉」(河合塾)
「日本史用語集」(旺文社)
「必携日本史用語」(実教出版)
「詳説日本史研究」(約560ページ、山川出版社)
「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(4冊1500ページ超、語学春秋社)
「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」(4冊1000ページ弱、ナガセ)
「これならわかる!ナビゲーター日本史B」(4冊1000ページ弱、山川出版社)
「山川 詳説日本史図録」(山川出版社)
「図説 日本史通覧」(帝国書院)
3.具体的読み方
【教科書の具体的読み方】
(1)最初の3周はサラッと読む
①頑張らない:覚えようと一生懸命にならず、歴史小説を読むように、軽い気持ちで、どんどん読み進めます。
これは読むストレスをある程度軽減し、挫折しにくくするためです。回数を読んだら理解も暗記もできるので、気楽に読みます。
②理解に努める:日本史は、暗記9割、理解1割です。理解が1割だとしても、理解しないと暗記しづらく忘れやすいので、意味が理解できない箇所・用語は、用語集や参考書で随時調べ、欄外に自分の理解を書いておきます。こうして教科書に情報を集約します。
③歴史の理解とは:人物の時代・業績が言える、用語の中身が言える、戦争や重要事項・テーマについて時代背景・因果関係(原因と結果)・主要人物・経過・後代への影響を言える、などを指します。
④1周目に全てを理解しようとしない:意味が分からない用語、理解できない文章があっても、1周目から全てを用語集や参考書で調べようとせず、せいぜい毎周、1ページ数個以内にします。
たくさん調べながら読むと時間がかかり、挫折する可能性が高くなるからであり、また、1周で理解できなくても、3~5周読めば理解できる箇所が増えるからです。
(2)4~6周目は流れを追う
①理解に努める:1~3周目と同様、4周目以降も、理解を深めるため、「なぜ?」「これは誰?」などと思ったら、毎周、1ページに数個以内を、用語集や参考書で調べ、理解し、理解した内容を教科書に書き込みます。
②歴史の流れを理解する:日本史ではよく、「流れ(時代背景・因果関係・経過・後代への影響)」を理解しろ、と言われます。それは入試や模試・テストに流れの問題が頻出するからです。
よって、「なぜこの戦争は起こったのか? 主要人物は? 結果とその影響は?」などと考えながら読み、その答えの箇所があったらマーカーを引き、理解します。
(3)9割暗記できたと思ったら暗記チェックをする
10~20周ほど音読して、9割暗記できたと思ったら、上記のように、「書きこみ教科書 詳説日本史」等の問題集を解き、キーワードとその意味をチェックします。
(4)9割暗記したら
10ページを10~20周し、9割暗記したら、次の30ページの暗記に取り掛かります。
4.教科書丸暗記列伝
また、当塾の生徒だけでなく、世の中には教科書の丸暗記をしてきた多くの先輩方がいます。そしてそこには多くの共通点があります。
「日本史教科書を10回読んで完全マスターした」
ブログ「 ワンランク上の勉強法」by 大場克彦(京都大学理学部卒)
……日本史をどうするかが問題であった。受験雑誌を見ていたら、合格者の体験談として、日本史は教科書を完全にマスターしたら合格点が取れると書いてあったので、それを実行することにした。
教科書を完全にマスターするためには、教科書を繰り返し読みなさい。その際、本文だけでなく、後ろについている年表や資料、さらに、欄外に書いてある補足説明や、絵の下に書いてある説明まで読みなさいと書いてあった。
日本史に取り掛かったのは10月に入ってからである。教科書は約300ページだったと思う。……4回ぐらいまでは、あまり覚えようと思わずに読んだ。5回目を読む頃には年が明けて受験が近づいていたので、友達と問題を出し合って答えるということもしていた。
7回目を読み終わって入試を迎えた。5回目を読んでいる頃は、友達の出す問題に答えられないことがあったが、7回目を読み終わる頃には、友達の出す問題に完全に答えることができるようになり、入試でも得点源の1つになった。
なお、本文に関しては、学校の授業の前に1~2回目を通し、授業を聴き、試験前に2~3回読んでいるので、入試の前までに11~13回読んでいることになることを付け加えておく。
1ヶ月で数十回黙読して世界史教科書を丸暗記した「スピードぐるぐる勉強法」
ブログ「司法試験情報局」by NOA
……12月の半ばになって、つまりセンターまであと1ヶ月という時期になって、突如、選択科目を世界史に変更することにしたのです。世界史はそれまで勉強したことがありませんでした。……文字通り、山川世界史一本勝負です。
やり方は単純で、まずひと回し目に、人名に赤マーク、その他の主要な事柄には黄マークをしました。そして、あとは ひたすら繰り返し教科書を読んでいくだけ という単細胞な方法です。……ともあれ、センターまでの1ヵ月間、闇雲ながらも、怠け者の割には結構頑張ったと思います。……正直、心の中では、「どうせ1ヶ月じゃ無理だよね・・」と諦めの境地になっていたのも事実です。
ところが、です。
これは我ながら非常に驚いたのですが、1ヶ月が経ち、センターまであと数日となった頃、自分がいつの間にか教科書の内容を全部覚えてしまっているという事実に不意に気づきました。ただひたすら教科書を読んでいただけなので、それまでは記憶の確認もしていなかったのですが、ふと思い立って頭の中で問題を作ってみると、それらの問題に全て答えられてしまう自分がいました。・・・
1ヶ月では絶対に無理だと思っていたのに、よく分からないけど「間に合ってしまった」ようでした。センター試験本番の得点はたしか89点だったように記憶しています。私には大満足な結果でした。
ちなみに、上で挙げた「勉強法」では、最初のマーク期間に1週間を費やして、その後の繰り返しはもの凄いスピードでやりました。1ヶ月で合計数十回(1日に2~3回)は読んだと思います。
これらの共通点は、10回以上教科書を読むこと。暗記できるまでしつこく読み続けることでしょう。
5.終わりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この文章があなたのお役に立てれば幸いです。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。