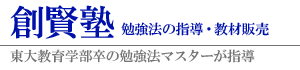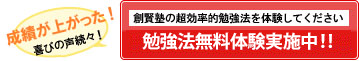このページでは暗記数学の具体的な進め方をご説明します。暗記数学とは、数学・算数・物理などの数学系科目で典型問題を最も効率的に習得する勉強法です。
目次
1.問題を5分考える
(1)解法を思いつかなかったら、5分で切り上げる
分かりそうだが、あれこれ考えても解法を思いつけなかったら、5分で切り上げて解答を見る。ここが暗記数学の第一のポイントである。全く新しい分野で知識がない場合は1~2分で解答やヒントを見ても良い。
(2)手が動いて解いている限り、5分を超えても良い
解法を思いつき、解法をあれこれ書いて解いていく限り、5分を超えて解いていって良い。
(3)図やグラフを描いてみる
いずれの場合も、図やグラフ、表、樹形図などを描いて、問題文を視覚化・具体化し、手を動かし続ける。
(4)ヒントを見ても良い
いずれの場合も、自力で解けそうになかったら、ヒント(指針やポイントなどの名で書かれた解答冒頭や欄外のヒント)を見ても良い。
(5)手が止まったら切り上げる
いずれの場合も、分からない、あるいは手が止まったら、切り上げ、諦めて解答を見る。
(6)正解への道筋が見えなかったら、10~15分で切り上げる
いずれの場合も、思いついた解法を書いて手が動いている限り、5分を超えても良いが、正解への道筋が見えなかったら、10~15分を限度に、諦めて解答を見る。
2.解法暗記:解答解説を読んで理解し、解法を暗記する
(1)正解の場合、添削し、次の問題へ
正解の場合、解答解説と自分の解答をよく見比べ、抜けがあったら赤ペンで書き加える。添削量が多くなければ、添削部分を見て記憶に努め、次の問題へ。添削量が多ければ、理解し、記憶して、再度解き直す。
(2)間違えたり解けなかった場合、正解への道筋のポイントを記憶する
問題文の横か上などに日付と印(×、正の字など)を付ける。自分の答案を赤ペンで添削し、正解までの道筋も書き写して理解し、記憶する。問題集の解答解説の思いつけなかった解法・間違えた箇所・詰まった箇所に印を付ける。
これは自分のノートではなく問題集に印を付け、そこを記憶する。解けなかった原因やどうすれば良かったかを理解し、ポイントを記憶する。このように、意図的に記憶するのが暗記数学の二つ目のポイントである。
(3)解法暗記のポイントは理解と記憶
解法暗記の段階のポイントは「理解」と「記憶」である。解答解説で理解できないことがあって、そこを記憶でカバーしたら、それは応用が利かない知識になる。可能な範囲で理解する。自分だけで理解できないことは、学校の先生などに聞いて理解に努める。ただし、完璧は求めない。だいたい理解できたら良しとする。多数の問題を解き、何度も復習していくと数学力が上がり、分かってくることも多いからである。
解答全体を理解したら、次に解答の要点や流れ(解法)を記憶する。見て記憶できる人は見て記憶し、見て記憶できない人は書き写して記憶する。
(4)正解しなかったら解き直す
きちんと解けた場合を除いて、記憶できたかどうかを確認するため、必ず直後に解き直す。直後に解かない人は成績が伸び悩むので注意が必要。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい中学生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】を開催しています。【中学生用:長期勉強法コース・短期セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
3.再現する:解けなかった問題は、すぐに再度解き、解答を再現
(1)忠実に再現する
解き直すときの注意点は、解答を、できるだけ忠実に「再現する」ということである。それにより、数学の正式な書き方を身に付けることができるからである。
また、解答を再現するときは、数式だけでなく、解答に書いてあった図やグラフ、表、日本語の補足説明などもできるだけ忠実に再現するよう努める。なぜなら、それらは解くのに必要だから、正解とみなされるのに必要だから、書かれているからである。
(2)再現に時間をかけない、思い出せなければ解答を見ればよい
再現するときの注意点は、再現するのに時間をかけないということである。ここは記憶の問題なので、1~2分思い出そうとして思い出せなかったら、すぐに、手が止まった箇所の解答部分を見てそれを理解し記憶する。そしてまた解き直し、再現し直す。最終的に自力で最後までたどり着くまで解き直す。
(3)解けなかったら、2回目の解き直しをする
再び解けなかったり、不正解であったり、抜けが多い場合、添削し、記憶して解き直す。
(4)正解であれば次の問題へ行く
自分の答案がほぼ解答通りの場合、添削し記憶して次の問題へ。
(5)1問に20分以上かけない
原則として、解けるまで何回も解き直すが、トータル20分以上はかけないようにする。自分にとって難しい問題は、1回で習得しようとしなくて良い。たくさんの問題を何回も復習していくと公式や定理、解法、数学的記述法などを身に付けていくので、だんだん難しい問題も解けるようになるからである。
4.問題を次々進め、章ごとに10回復習する
(1)二週間以内に復習に入り、10回復習し、「スラスラ状態」にする
数学の「理解」も「記憶」なので、1ヶ月以上は持たない。まだ記憶に残っているうちに復習しないと、復習にかかる時間は1回目と変わらなくなり、なかなか終わらないことになる。
復習が2週間以内だと、まだ記憶に残っているので、1回目の5~7割の時間で済む。よって、2週間以内に進んだ範囲を1セットにし、すぐに2周目に入り、それが終わったらまた即3周目に入る。そうやって、同じセットを10回前後復習し、解答解説が理解できる問題は全問、スラスラ解けるようにする。
(2)章ごとに復習する
区切りが良い範囲をセットにする。章ごとに復習するのが良い。2週間以内に1章を終えるのが理想。
(3)日曜日ごとに復習する
2週間進んだ分を総復習するのとは別に、日曜日(もしくは時間が取れる別の曜日)を復習日にして、毎週進んだ分だけ各科目復習する。
復習間隔は短い方が良いため。復習時間は取れる時間によるが1時間程度でよい。1問ずつ解き直す時間があれば書いて解き直し、時間がなければ見て解法を思い浮かべ、解答を見る、という感じでも良い。
(4)復習は時間が節約できる
「5回も10回も復習するのは時間のムダだ。先へ先へ進むのがよい」と考える人は多いだろう。しかし、これは大いなる誤解である。
その理由は2つある。1つは、復習は実際には時間がかからないからである。2週間以内に復習すれば、復習1回目は最初の約半分の時間で済み、2回目は1回目の約半分の時間で済む。こうして5回目は最初の約10分の1の時間で済み、10回目は最初の約100分の1の時間で済む。ここまで復習すれば、ほとんどの問題が「スラスラ解ける状態」になる。10回の復習は、効果が絶大な割に、時間がかからないのである。
2つ目の理由は、復習しなかったら、できなかった問題は2~3週間もたてばできなくなるからである。できなくなったまま放置すれば、勉強時間がそれこそムダになる。
5.問題集を最後まで進める
第一セットを10周したら第二セットに入り10周する。同様にして問題集の最後まで進める。
6.全問スラスラ解けるまで復習する
(1)セットごとに10周⇒全体を5周
最後の章まで終えたら、全体の2周目に入る。2周目は×印が2つ以上の問題を優先的に解いていき、全問スラスラ解けるまで習熟する。全体の復習回数の目安は5~10回前後。
(2)全問スラスラ状態になったら次の問題集へ
自分にとっての難問以外の全問、「問題を見たらすぐに解法が思い浮かぶ状態」「スラスラ解ける状態」になったら、次の問題集へ進む。
(3)全問スラスラ状態にする利点
とにかく1冊を徹底的に復習し、全問「問題を見たら解き方がスラスラ分かる状態」にすることが重要だ。そうなって初めて長期記憶に入り、数ヶ月以上忘れない記憶になるからである。また、そうなったら、基礎・標準問題の組み合わせである応用問題を解く際にも、解法をすぐに幾つも思い付けるようになるからである。
7.終わりに
以上暗記数学の実際の進め方を述べました。
参考にしていただけると幸いです。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい中学生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】を開催しています。【中学生用:長期勉強法コース・短期セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
【テスト後の分析に感心しました】
Mさん(中学2年生、愛知県)
中間テストを終えて
先生に勉強方法を教わり始めて2カ月、中間テストがありました。本人はテストの出来栄えは、今までより出来た気がする、勉強のコツが分かってきた!と言って帰ってきました。結果、4教科で順位が上がりました。
■1年2学期期末テスト:英60点(75位)、数57点(82位)、国73点(33位)、理70点(75位)、社61点(86位)、5教科総合76位/150人。
■2年1学期中間テスト:英60点(47位)、数64点(61位)、国72点(54位)、理68点(64位)、社66点(74位)、5教科総合60位/150人。
そしてテスト後、テストの分析がはじまります。これも、今までやってこなかった勉強法でした。間違えた問題が、なぜ間違えたのか?を分析し、ルーズリーフにまとめていきます。この分析が、慣れないのもあるのか、とてつもなく時間がかかりました。
ですが分析をすることで、間違えた原因が明確化するのです。その後、再度解きなおす。数学は口頭再現法、英語は瞬間英作文です、これを繰り返す。
天才がいかに丁寧に勉強をしているのか、と感じた瞬間でした。
テスト見直しは、手間でやりたくないという気持ちが出てしまう勉強ですが、手を抜かずにやっていくことが成績を上げる近道だと思いました。本人はまだまだです、自主的に取り組んでくれるようになるといい、と思っています。