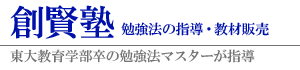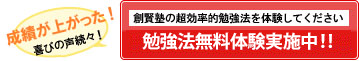数学の成績をダントツに上げるには、「暗記数学と10回復習」で「問題を見たらすぐに解法が思いつくようにする」ことが役立ちます。
そしてもう1つは口頭再現法です。口頭再現法については【数学勉強法(2)10分で解き方を暗記する口頭再現法】参照。
目次
1.数学の2つの勉強法
1.1.とことん考える派と暗記数学派
数学には2つの勉強法があります。一つは、解けるまで20分でも30分でも考える方法です。二つ目は5~10分は一生懸命考えるが、それで糸口が見つからなければ諦めて、解答解説を見、その解法(解き方)を理解し覚えて、再度解くという暗記数学の方法です。
1.2.普通の高校生には暗記数学がオススメ
前者は、数学者になろうという人、思考力をとことん磨きたい人、時間が有り余っている人には向いていますが、普通の人がとことん考えていたら、時間がいくらあっても足りません。高校生、受験生は基本的に勉強時間が足りないのですから、普通の高校生は、まずは、暗記数学で入試必出パターンを記憶してから、時間があれば、入試問題等をとことん考える方法の方が、数学の勉強法としては適しているでしょう。
よって、当塾では暗記数学の方を推奨しています。以下では、暗記数学の方法とその前提となる考え方について述べていきます。
2.暗記数学とは
暗記数学とは、東大医学部卒の精神科医で、受験技術研究家・大学教授でもある和田秀樹氏が言い始めた数学の勉強方法で、「大学受験数学の問題には一定の数の解法パターンがある。その解法パターンを、”理解”した上で”暗記”すれば、効率よく成績を上げられる。一流大学の入試問題でもこの方法で攻略が可能である」というものです。
暗記数学を邪道と考える人は勘違いしています。そもそも、思考するには材料たる「知識」が不可欠です。人間は知識をもとに考えているのです。よって、数学を解くときも、知識(公式や定理、基礎知識、解法)をもとに考え、解を導きます。そのもとになる知識が少なければ、解けないので、先に知識を入れてしまおうというのが暗記数学のコンセプトです。至極真っ当な考え方です。
参考文献:「数学は暗記だ」(和田秀樹著、ブックマン社)
※以下の当塾の暗記数学の方法は、和田氏の方法、上記の本を参考にしてはいますが、両者はかなり異なります。
3.暗記数学の前提と手順
暗記数学の前提にある考え方は以下の2つです。
3.1.暗記数学の前提にある考え方
(1)大学入試問題にはパターンがある
大学入試の数学の問題には、無限のバリエーションがあるわけではなく、典型問題、すなわち、典型的な解法を使うパターン問題が、数学1A、2B、3で、各300前後存在する。実際の入試には、その典型問題と、典型問題の組み合わせである応用問題がほとんどを占める。よって、いち早く入試問題を解けるようになりたければ、その典型問題と応用問題の解法を理解し記憶してしまえば良い。
(2)問題を解くときは「記憶」を使っている
高校生が数学の問題を解いているとき、「考えている」と言うが、実際には何をしているかというと、「以前に解いた類似の問題の解き方を思い出そうとしている」か、「その解き方をいろいろ試している」に過ぎない。ゼロから解法を思いつくなどということはほとんど無いと言って良い。よって、問題を解けるようになるには解法を多く記憶するのが先決。そのあと存分に考えて解けば良い。
3.2.暗記数学の手順
【暗記数学の手順】
(1)問題を5分考える:解法を幾つか試し、5分たっても正解への道筋が見えてこなかったら、諦めて解答を見る。
(2)解法暗記:解けなかった問題の解答解説を読み、理解し、解法を暗記する。
(3)再現:すぐに再度解き、解答を再現する。きちんと再現できるまで、理解し記憶し再現することを繰り返す。
(4)1問当たり15~20分以内で解く:難問でも時間をかけすぎない。20分以上かかる場合は自分の現状の能力を超えていると考え、早めに切り上げて次へいく。
(5)即答:全問、スラスラ解ける状態にする。問題集マスターの基準は、「全問、問題を見たら解法を即答できる、スラスラ解ける状態」。そこまで習熟して初めて忘れない記憶になり、応用問題が解けるようになる。
(6)復習:復習間隔は2週間以内で、5~10回復習する。「全問、スラスラ解ける状態」にするまでの復習回数の目安は、数学力や復習周期により異なるが、5~10回前後。復習間隔は2週間以内。忘れる前に復習する。
暗記数学の全体像は以上の通りです。詳細は下で詳しく書いています。
4.暗記数学は時間対効果が高い
私自身は受験生時代、自力で解くことにこだわった「とことん考える派」でしたが、これは時間対効果(かけた時間に対して成績がどの程度上がるか)は低いと思われます。たいていの高校生が自宅で1日に数学に割ける時間は1時間前後ですから、解けるまで15分も20分も考えていたら、結局解けない場合も考えると、1時間にせいぜい2~3問しか進みません。暗記数学なら、5分以上は考えないので、1問平均15分、1時間に4問前後解けることになります。400問の問題集をするとして、暗記数学では100日前後で1周しますが、とことん考える方法では160~200日かかります。全て習得できるまでの時間を考えると、両者には2~3倍の開きが出るでしょう。
5.大学受験数学はヒラメキより「記憶」で解くものである
数学の問題を解いているとき、普通の高校生がその時実際には何をしているかというと、考えているというより、「思い出そうとしている」場合が多い。過去に覚えた公式、基礎知識や解き方を思い出そうとしているのです。そうではありませんか?
一方、当然、考えている人もいるでしょう。その「考えている」とはどういうことかというと、「この解き方はどうかな、あの方法でもいけるかも、では試してみよう、あ、ダメだった。ではこの方法は? あ、上手くいった」。これを「考えている」と言うのです。
しかし、これも、「ゼロから発想している」のではなく、「記憶に入っている解き方を一つずつ試している」に過ぎません。つまり、「ヒラメキ」というより、「記憶」で解いているのです。これが大学受験数学の実態です。
創賢塾のホームページに書かれた数学・英語等の勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
6.暗記数学で解法パターンを習得すれば成績は上がる
6.1.大学受験数学の解法パターンは限られている
大学受験に出る数学の解法パターン(問題パターン)は無限にあるわけではなく、数百個に限られています。それは、大学受験問題が、文部科学省の「学習指導要領」に縛られているからです。
例えば、定評ある網羅系問題集の代表である「青チャート(チャート式基礎からの数学)」(数研出版)では、「数学1+A」の例題数は300超、「数学II+B」は400超、「数学3」は300弱です。他の網羅系問題集でも、数はそれほど変わりません。また、共通テスト用では、「チャート式共通テスト対策数学1A+2B」(数研出版)の例題数はわずか200弱です。
これらを習得すれば成績も上がり、たいていの大学、もしくは共通テストの問題に対処することができます。
要するに、入試問題として出てくるのは、基本的に、限られた解法パターン(問題パターン)とその組み合わせだけなのです。したがって、その限られた解法パターンをまず習得し、いつでも解けるようにした後、応用問題や過去問の解法パターンを習得すれば良いことが分かります。
そして、その「解法パターンの”習得”」とは、言い換えれば、「解法パターンを理解して記憶する」ということにほかなりません。
6.2.一問にかける時間は少なければ少ないほど有利
しかし、「限られた解法パターンをまず習得」と口で言うのは簡単ですが、実際にはほとんどの人が青チャートのような分厚い問題集を1周することさえできないのが現実です。
青チャートでは、数学1+AとII+Bで、例題数が700超、応用問題も入れると1300超(練習問題=類題は除く)もあります。1300問を1問平均15分で解いたとしても、1周330時間かかります。1日2時間で160日超、5ヶ月です。3周したら、1年は超えるでしょう。かなり時間的に厳しいと言わざるを得ません。
解けない問題を15分、20分と考え続ける勉強法では無理があることがお分かりいただけると思います。
対策としては、①もっと問題数の少ない問題集に換える(もしくは分厚い問題集の基本例題、重要例題、応用問題ごとに分けて習得していく)、②1問当たりの時間を減らす(暗記数学を実践する)、③勉強時間を毎日2~3時間以上取る、の3つしかありません。勉強時間を増やせればOKですが、それが難しい場合は、①か②、もしくは両方を実践するしかありません。
当塾では、偏差値が60以下で、毎日の数学勉強時間が2時間以下の人は両方を、60以上で2時間以上取れる人も、両方かどちらかを実践するよう指導しています。
6.3.基礎からマスターする:問題には習得する順序がある
どの科目でも、理解し記憶すべき内容には順序があります。
数学で言えば、まずは基礎・標準問題を完全に理解し記憶して、いつでもスラスラ解けるようにしてから、応用問題に入るのが効率の良い方法です。つまり、基礎・標準問題だけをまず5~10周して習得してから、応用問題に入るのが良いのです。なぜなら、応用問題とは、基礎・標準問題の解法と応用的な解法の組み合わせで成り立っているので、基礎・標準問題の解法があやふやなまま、応用問題を解いても、なかなか解法を思いつけないからです。
問題集に500問の問題が載っているとして、その500問には、基礎問題があり、その基礎の上に標準問題、その上に応用問題が乗っています。
よって、教科書レベルが怪しい人はまずは基礎問題(基礎的な解法・公式・定理)を理解し記憶し、「スラスラ解ける状態」にしてから、標準問題(標準的な解法・公式・定理)に入り、それを理解し記憶する。
教科書レベルが身に付いている人は、基礎・標準問題を理解し記憶し、「スラスラ解ける状態」にしてから、応用問題に入る。
数学が得意な人(偏差値60~65以上)は、基礎・標準問題と応用問題を並行して解いても良いでしょう。
しかし、一般的にはこのような順序で勉強せず、基礎問題も応用問題も、1冊の問題集の中にある問題は一緒に解いていきます。そして5回以上復習することはマレです。その結果、基礎問題も応用問題も、理解・記憶とも曖昧で、解くのに時間もかかります。
広く薄く(多くの問題を少ない回数解く)より、範囲を絞って深く(より少ない問題を5回以上)解いていく方が、結果的に早く成績が上がります。ぜひ試してみてください。
6.4.数学の問題は階層構造になっている
大学受験問題の解法は、教科書レベルの解法(基礎知識・定理・公式)と大学受験レベルの解法(基礎知識・定理・公式)の組み合わせであり、教科書レベルの解法は、中学数学レベルの解法と、高校教科書レベルの解法の組み合わせです。
そして、大学受験応用問題・難問は、それら全ての解法の組み合わせで成り立っています。
つまり、こういうことです。
【中学数学の解法+教科書レベルの解法+大学受験レベルの解法⇒大学受験応用問題・難問の解法】
よって、中学数学~大学受験レベルの解法が即座にサッと頭から出てくる状態にしていれば、応用問題が解ける可能性が高まり、逆に、一つ一つを思い出すのに時間がかかったり、思い出せなければ、それだけ、解法を思いつく(組み合わせを思いつく)のにも時間がかかり、あるいは解けないことになるわけです。
6.5.穴があればふさぐ
中学数学に抜けがあれば、中学数学を復習する必要があり、高校教科書レベルに抜けがあれば、先を急ぐより、教科書レベルの復習をする必要があります。
「高校教科書レベルに抜けがある」とは、具体的に言えば、「教科書の問題の解答解説を読んで意味が分からないところがある」ということです。意味が分からないのは、頭が悪いのではなく、数学の才能がないわけでもありません。ただ、それ以前の解法(基礎知識・定理・公式)、つまり、高校教科書の該当部分以前の内容と中学数学の知識に抜けがあり、即座に出てくるようになっていないだけなのです。
よって、対処法としては、高校教科書の以前の部分を徹底的に復習して解法(基礎知識・定理・公式)を記憶すること、そして、そこでも理解できない部分が結構あれば、中学数学を徹底的に復習し解法を習得することが必要になります。
同様に、大学受験レベルの問題の解答解説を見ても分からない部分が多いときは、それ以前のどこかの基礎知識に抜けがあるからです。よって、大学受験レベルの問題集で分からないことが多い場合は教科書レベルに戻り、教科書レベルで分からないことが多い場合は中学レベルに返り、徹底的に復習をしてスラスラ解ける状態にしてからレベルアップしていくのが正しい勉強法です。
6.6.暗記数学で解法パターンを習得すれば成績は上がる
以上から言えることは、中学数学と高校教科書と大学受験レベル問題集の解法パターンの一つ一つを、できるだけ即座に引き出せるようにトレーニングしておけば、高得点を取れ、成績が上がる可能性が高まるということです。
そして「即座に引き出せるようにする」には、復習しかありません。「解法を即座に思い出せるまで一つ一つの問題を何度も復習する」、具体的には、5回以上復習する。それが数学の受験勉強の基本戦略になります。
そしてそれを最も効率よく短期間で達成する方法が暗記数学です。
7.数学学習の指針
以上をまとめると、創賢塾の数学学習の指針は、以下の4つになります。
【創賢塾の数学学習の指針】
(1)薄い問題集:出来るだけ問題数を絞った、薄い問題集を選ぶ。問題集のレベルは今の数学力により、基礎問題集、受験標準問題集、難問問題集を選ぶ。
(2)暗記数学:暗記数学の手法で、まずは教科書、次に受験基礎&標準問題、次に応用問題・難問の解法を理解して暗記する。
(3)徹底的な復習:復習を徹底的に行い、解答解説が理解できる問題は全て、「問題を読んだらすぐに解法が思い浮かぶ状態」にする。
(4)復習10回:「問題を読んだらすぐに解法が思い浮かぶ状態」にするための復習回数の目安は5~10回。
8.数学における「記憶」と「理解」
以上から分かることは、受験数学では、「記憶量(記憶した解法パターンの量)」がものを言うということです。解法パターンを効率よく記憶していく暗記数学の優位性がここにあります。
そしてその記憶の前には、「理解」があります。全過程を丸記憶しているのではなく、ポイントポイントを理解して記憶し、残りは数学の規則、計算のパターンとして覚えていて、記憶しなくても計算力があれば解けていきます。
9.暗記数学に適した教材
教科書や問題集はすべて暗記数学の要領で解いて記憶していきます。そしてどの問題集が自分に適しているかは、今の数学力によって変わってきます。
9.1.数学が苦手な人(偏差値50以下)の場合
偏差値が50以下の場合、中学レベルの基礎が分かっていないことが多いので、できるだけ中学レベルから復習します。まずは、中学数学レベルから復習しながら高校数学を教えてくれる以下のような問題集に取り組みます。
「スバラシク面白いと評判の初めから始める数学」シリーズ(マセマ)
「とってもやさしい数学」の高校数学シリーズ(旺文社)
「やさしい高校数学」シリーズ(学研)
これで分からない部分が結構あれば、中学レベルからやり直します。
「やさしい中学数学」(学研)
「高校入試合格BON!数学」(学研教育出版)
「高校入試突破計算力トレーニング」(桐書房)
この後は次項の問題集を解いていきます。
9.2.普通の成績の人(偏差値50~60前後)の場合
このレベルの人も中学レベルに不安はありますが、まずは教科書レベルをマスターしていきます。
高校の教科書レベルは、教科書(+教科書ガイド)か、解説の詳しい問題集や講義系問題集を使うことで、習得します。
「学校の数学教科書」+ガイド
「スバラシク面白いと評判の初めから始める数学」シリーズ(マセマ)
「スバラシク強くなると評判の元気が出る数学」シリーズ(マセマ)
「沖田の数学をはじめからていねいに」シリーズ(東進)
「高校これでわかる数学」シリーズ(文英堂)
もし、以上の教科書・問題集を使っても分からないところが結構あるなら、思い切って中学レベルを一度おさらいしましょう。
計算練習もやった方が良いでしょう。
「大学入試・共通テスト突破計算力トレーニング 上下」(桐書房)
この後は、共通テストのみの人は共通テスト対策として、解説の詳しい、難しすぎない問題集を暗記数学でマスターしていきます。
「スバラシク得点できると評判の快速!解答共通テスト数学」シリーズ
「チャート式共通テスト対策数学1A+2B」(数研出版)
「共通テスト 数学I・A よく出る過去問トレーニング」(中経出版)
「共通テスト 数学II・B よく出る過去問トレーニング」(中経出版)
「文系・共通テスト対策数学12AB入試必携168」(数研出版)
二次試験で数学がある人は更に、過去問を解き、過去問レベルの問題集を探して解いていきます。
「各大学の過去問」(教学社)
「スバラシクよくわかると評判の 馬場敬之の合格!数学」シリーズ
「理系対策数学12AB/3入試必携168」(数研出版)
「文系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B」(河合出版)
「理系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B 」(河合出版)
「チャート式解法と演習数学(黄チャート)」シリーズ(数研出版)
「チャート式基礎からの数学(青チャート)」シリーズ(数研出版)
9.3.数学が得意な人(偏差値60~65以上)の場合
共通テストしかない人は上記共通テスト対策問題集をマスターします。
二次試験がある人や理系の難関私立志望者は、上記の問題集を参考に、自分の実力・勉強時間・入試問題の難易度に応じて問題集を選びます。
10.終わりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
あなたの健闘を祈ります。
創賢塾のホームページに書かれた数学・英語等の勉強法をいち早く習得したい高校生のために【5教科のテスト勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【高校生用:講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
【第一志望の法政大学に合格できました】
Tさん(高校3年生、神奈川県、法政大学キャリアデザイン学部[偏差値60]合格)
第一志望の法政大学のキャリアデザイン学部(河合塾偏差値60)に合格することが出来ました。
教えていただく前は(河合塾)偏差値45~49前後でしたから、先生の授業がなければ、合格はなかったと思います。
全然解けなかった国語が、短い時間で要点を探して読めるようになり、学校のテストの偏差値も、模試の偏差値も10以上、上がりました。
毎回、先生に教えられたやり方で過去問の文章にキーワードとキーセンテンスに印を付けながら読み、授業でチェックしていただき、問題の解き方や内容を、徹底的に教えていたことで、読み方や解き方が身に付いたお蔭です。
英語も、先生に薦めて頂いた「入門英文解釈の技術70」「基礎英文解釈の技術100」がとても良かったです。英文解釈をやったお蔭で、英語長文への苦手意識が減り、分かる英文が飛躍的に増えました。英語が苦手なのでこれからも頑張っていきたいです。
数学も、先生に薦めて頂いたマセマの「初めから始める数学」「元気が出る数学」「合格数学」がとても良かったです。学校の「青チャート」よりずっと分かりやすく、進めやすかったです。それと口頭再現法で過去問が解けるようになりました。数学にして良かったです。
本当にありがとうございました!
【数学の成績が上がった】
Yさん(高校3年生、京都府)
3か月ほど前(2年生の1月)に、個別指導(駿台個別)の数学の先生に言われて共通試験の過去問の数学を解いてみました。結果、数学Ⅰ+A、Ⅱ+Bともに7割ほどでした。その先生は今の段階でこの点数が取れるのはなかなかいい調子だと言ってくれました。
ここまで数学の成績が上がったのは創賢塾で教えてもらった口頭再現法などの勉強法のおかげです。数学だけでなく、ほかの科目の成績も、例えば、
コミュ英語:15点(平均49点)⇒59点(平均48点)、
論理表現:16点(同49点)⇒62点(同48点)、
数学II:42点(同55点)⇒30点(同30点)、
数学B:25点(同58点)⇒49点(同53点)、
古典:35点(同64点)⇒77点(同67点)、
物理:15点(同40点)⇒46点(同29点)、
化学:43点(同62点)⇒95点(同70点)、
地理:27点(同61点)⇒50点(同63点)などに上がりました。
高校に入学してからの私は何を勉強してよいかわからず、成績も悪いままで、無気力になっていました。そんな私に勉強のやる気を起こさせてくれたのは創賢塾でした。だから、私にとって創賢塾との出会いはチャンスだと思います。
このような大事なチャンスを手に入れた以上は志望校合格に向け一生懸命努力していこうと思います。