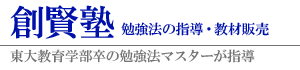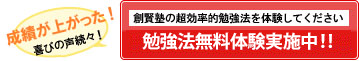このページでは日本史の流れの理解・暗記に役立つ、日本史年表の暗記法について書いていきます。
1.年表暗記
1.1.年表を暗記する
通史暗記中、もしくは通史暗記後に、教科書の巻末にある8~10ページほどの年表(年代、最高権力者名、政治・経済・社会の出来事、文化)を暗記します。
また、時の最高権力者名を順番に言えるように暗記します。
1.2.年表暗記の重要性
年表には、重要な歴史用語が、権力者名と共に年代順に書かれており、これを暗記することで、日本史の大きな流れを正確に記憶でき、知識が整理でき、共通テストや私大入試で頻出する「年代順並べ替え問題」が得意になります。
また、最高権力者名を順番に暗記することで、歴史の流れがより明確になります。
1.3.暗記の目標
「(政治・経済・社会の)歴史用語⇒年代・最高権力者名」「年代⇒最高権力者名・歴史用語」を即答できるように暗記します。
「文化の歴史用語」は「(政治・経済・社会の)歴史用語」を暗記した後で暗記、その後、最高権力者名を順番に暗記していきます。
「世界の歴史用語」は重要性が低いので暗記しません。
2.暗記の工夫
2.1.ゴロ暗記
年代はゴロを使うと暗記しやすいです。以下のようなゴロ年代暗記本を使います。
「元祖 日本史の年代暗記法」(旺文社)
「まんが必修年代暗記法日本史」(文英堂)
「高校100%丸暗記 日本史年代」(受験研究社))
「トマスの日本史-1000ダケヨ―日本史総合図解年表と年号暗記法」(聖文新社)
「新 日本史 頻出年代暗記」(学研教育出版)
「元祖 日本史の年代暗記法」がオススメです。暗記法は【「元祖 日本史の年代暗記法」習得法】参照。
2.2.年表で暗記する順番
入試問題を解くときには、「年代⇒歴史用語」と「歴史用語⇒年代」の両方が必要ですが、「歴史用語⇒年代」の方が遙かに必要とされます。
よって、暗記する際には、「歴史用語、年代(ゴロ)、最高権力者名」の順に暗記するのがオススメです。例えば、「平城京に遷都、ナットウ(710年)、元明天皇」のように。
その後、「年代⇒最高権力者名・歴史用語」も暗記します。
2.3.セット法
年表暗記は、半ページや1ページなどを1セットにし、1週間で30~40周音読して暗記していきます。
毎週半ページなら16週間(約4ヶ月)、毎週1ページなら8週間(約2ヶ月)で暗記できます、
ここでは毎週半ページ暗記するとして書いていきます。
通史暗記中に暗記する場合、通史暗記している範囲の年表を暗記します。
2.4.記憶の原理
記憶には3種類あり、まず全ての情報は短期記憶(数時間~数週間もつ記憶)に入り、7日(7回)前後復習することで中期記憶(数週間~数ヶ月もつ記憶)に入り、更に2ヶ月以上復習することで長期記憶に入ります。
長期記憶に入れなければ入試で使える情報にはなりませんから、受験勉強では、全ての重要情報を長期記憶に入れることが目標になります。
3.年表暗記法
【教科書年表暗記法】
(1)第1セット:暗記法:【「歴史用語、年代(ゴロ)、最高権力者名」×10~20回音読⇒暗唱⇒次へ⇒半ページ×1日5周×7日(35周前後)】
①第1セット半ページ:「(政治・経済・社会の)歴史用語、年代(ゴロ)、最高権力者名」の順に、暗唱できるまで、10~20回前後音読します。
例えば、【「平城京に遷都、ナットウ(710年)、元明天皇」×10~20回前後音読⇒暗唱】。
暗唱できたら次へ。半ページ暗記したら最初に戻って「1セット1日5周×7日(完全に暗記するまで)」。
1日5周してまだ時間があれば、次の半ページを同様に暗記します。
②4日目から毎日テスト:「歴史用語⇒年代(ゴロ)・最高権力者名」「年代(ゴロ)⇒最高権力者名・歴史用語」の両方をテストし、即答できたら外し、残りに印を付け、同様に暗記します。
その日の最初にテストして、ほぼ全部即答できたら第1セットは外して、第2セットへ。
③即答が重要:テストして3~5秒後に言えても、まだ記憶が浅い(=短期記憶にしか入っていない)のですぐ忘れます。
「即答=中期記憶に入った印」なので、数週間~数ヶ月忘れません。
(2)第2セット以降
①暗記法は同じ:同様に7日前後で第2セットを30~40周音読して全て暗記したら第3セットへ進みます。以後同様に年表の最後まで進めます。
②既習全セットを復習:先へ進むと同時に、既習部分を【「1セットをテスト⇒暗記」×1日10分×週2回×既習全セット】のように復習します。
(3)全体2周目以降
①全体2周目:年表の最後まで進んだら、すぐに全体2周目に入り、1セットずつ、【「歴史用語⇒年代(ゴロ)・最高権力者名」「年代(ゴロ)⇒最高権力者名・歴史用語」両方のテスト⇒即答できない用語・年代に印⇒1セットを5周暗記⇒次のセットへ】のように暗記していきます。
「毎日1ページ×8日で1周」のように進めます。
②「文化の歴史用語」の暗記:全体を3~5周し、「(政治・経済・社会の)歴史用語」の箇所をほぼ全て即答できるようになったら、「文化の歴史用語」の暗記を加えます。
【「文化の歴史用語⇒年代(ゴロ)」×10~20回前後音読⇒暗唱⇒次へ⇒半ページ×1日5周×7日(35周前後)】
③全体を10周以上復習:「文化の歴史用語」を暗記しながら、「(政治・経済・社会の)歴史用語」の復習を毎日行い、2ヶ月以上かけて、全体を10周以上復習し、長期記憶(数ヶ月~数年以上もつ記憶)に入れていきます。
※長期記憶に入れるには2ヶ月以上の復習が必要です。
(4)最高権力者名を暗記する
①暗記対象:教科書本文に名前・事績が出ている最高権力者(例:古代の天皇・各幕府の将軍・明治以降の首相)の名前を、7~10名前後を1セットにして、順番に暗記します。
②暗記法:【「1セットの最高権力者名を、暗唱できるまで、10~20回前後、順番に音読する⇒暗唱」⇒次のセットを音読・暗唱⇒時間がある限り先へ×7日(即答できるまで続ける)】。
4日目からテストし、正しく即答できたらそのセットは外します。
③具体例:江戸時代の15人の将軍名を暗記する場合:15人を一気に暗記するのは難しいので、2つか3つのセットに分けて、【「家康、秀忠、家光、家綱、綱吉……」×10~20回前後音読⇒暗唱⇒次のセットへ】のように1セットずつ暗記していきます。
④復習:毎週次のセットに進みながら、既習全セットを【「テスト⇒即答できなければ10~20周前後音読⇒暗唱」×週2回×既習全セット】のように復習します。
4.終わりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この文章があなたのお役に立てれば幸いです。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために、自宅で受講できる【5教科の受験勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【オンライン講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。