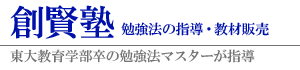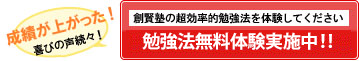【日本史の論述対策】シリーズでは、2次試験に日本史の論述問題がある国公立大志望の受験生を対象に、共通テスト、論述問題で合格点を取るための暗記戦略について書いていきます。本格的な論述のある難関私立大学の論述対策も、このシリーズが参考になるはずです。
このページは、通史暗記についてです。
「難関私大受験生」の日本史勉強法はこちら、「共通テストのみの受験生&中堅私大志望者」の日本史勉強法はこちらに書いています。
1.日本史暗記の全体像
2次試験に日本史の論述問題がある国公立大志望の受験生の日本史暗記の全体像は以下の通りです。暗記の目標、その際使う教材の種類、使用順序、オススメ教材、そして暗記法も紹介していきます。
【日本史暗記の全体像】
(1)目標1:記憶の軸を作る
①記憶の軸とは:日本史のように膨大な知識を暗記しようとするとき、最初から細かい知識まで暗記しようとするのは非効率的です。忘れやすいからです。
枝葉の細かい知識ではなく、まず根や幹に相当する事項(時代・天皇・権力者・各時代の代表的な出来事とその順序)や歴史の流れ・俯瞰的知識を暗記し、記憶の軸を作ると、それが記憶のフック(鉤=カギ)となり、細かい知識を暗記しやすくなります。
②歴史の流れとは:重要歴史用語(法律・戦争・人物等)についての「時代背景・原因・理由・目的・因果関係・主要人物・経過・結果・後代への影響」のことです。共通テストでも難関大入試・論述試験でも、歴史の流れの問題は頻出ですから、流れを理解し暗記することは最優先・最重要です。
③俯瞰的知識とは:「歴史の流れプラス、政治・経済・文化等の特定のテーマに関する特徴・比較・意義」のことです。つまり、歴史を大きな視点で整理した内容を指します。論述問題では、主に、俯瞰的知識が問われます。
④オススメ教材・時期:できるだけ、通史暗記前の1~2年生のうちに、内容が少なく読みやすい「学研まんが NEW日本の歴史」(全12巻、学研)のようなマンガや、「超速!最新日本史の流れ」(全2冊、合計420ページ、ブックマン社)のような概説書を10周以上読んで、あるいはスタディサプリなどの動画授業を1~2周見て、記憶の軸を作るのがオススメです。
(2)目標2:通史暗記をする
①通史暗記とは:歴史の流れと用語を一通り暗記し、共通テストレベルの問題で7~8割以上、取れるようにすることです。
通史暗記をいかに早く終わらせるかが受験勉強の課題になります。
②2種の用語暗記:用語暗記には2種あり、1つは、穴埋め問題集や一問一答問題集により、人名や歴史用語、年代を言える(書ける)ように暗記することで、これが普通の用語暗記です。
もう1つは、重要な歴史用語の意味・中身を言えたり、人物の業績を言えるように暗記することで、これを用語の意味の暗記と言います。
論述問題対策には、特に用語の意味の暗記が重要になります。用語の意味は、教科書を10周以上読んで暗記したり、「書いてまとめる日本史―日本史短文論述練習帳」(石川晶康著、河合塾)のような短めの論述問題を集めた問題集で暗記していきます。
③オススメ教材セット1:「時代と流れで覚える! 日本史B用語」(165ページ、文英堂)のような共通テストレベルの流れ&用語暗記本か、「日本史B一問一答【必修版】」(東進)のような一問一答問題集を暗記のメインにします。
暗記法は【「時代と流れで覚える! 日本史B用語」暗記法】、【「東進 日本史B一問一答【完全版】」暗記法】参照。
教科書は共通テスト、2次試験論述問題の出典ですから、理解用教材には教科書が最適です。10~20周以上読んで理解し、暗記していきます。
教科書で理解しづらい箇所は「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(語学春秋社)などの参考書で調べ、理解します。
④オススメ教材セット2:教科書丸暗記法:教科書を理解用だけでなく暗記用としても用いる方法です。
具体的には、40ページなどのセットごとに、10~20周音読するか、20周以上黙読して暗記していきます。詳細な暗記法は【日本史暗記法(3)日本史教科書を丸暗記する方法】参照。
教科書は共通テスト、2次試験論述問題の出典ですから、論述対策としては、教科書を丸ごと暗記するつもりで読み続けるのが王道の勉強法です。
理解と暗記のチェックのため、「日本史B一問一答【必修版】」や「時代と流れで覚える! 日本史B用語」を使います。また、教科書で理解しづらい箇所は「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(語学春秋社)などの参考書で調べ、理解していきます。
⑤年代&年表暗記:難関大学志望者は、「元祖 日本史の年代暗記法」(旺文社)のような年代(年号)暗記本を1冊暗記し、教科書の年表、権力者の暗記も行います。
⑥補助教材:通史暗記時には、用語や人物の業績を調べるための「日本史用語集」(山川出版社)のような用語集、歴史の流れを理解するための「石川晶康 日本史B講義の実況中継」や「詳説日本史研究」(約560ページ、山川出版社)のような参考書、史料の解説や現代語訳が載っている「詳説日本史史料集」(山川出版社)のような史料集、写真や絵、年表・系図などを視覚的に見て理解する「山川 詳説日本史図録」(山川出版社)のような資料集を補助として用い、理解を深めます。
(3)目標3:共通テスト対策をする
①「ベストセレクション 共通テスト 日本史B重要問題集」(200ページ弱、実教出版):通史暗記をした後、本書のような共通テスト過去問問題集を10周して、全問、理解して即答できるように暗記します。
②共通テスト過去問問題集とは:共通テスト・センター試験過去問約15~20年分を時代順・分野別に配列し直して編集した問題集のことです。
共通テスト過去問問題集を暗記したら、共通テスト過去問・模試で7~8割以上は取れるようになるはずなので、その後は、論述対策と共通テスト過去問を並行して進めていきます。
③共通テスト過去問10年分以上:週1年分など解き、暗記し、8~9割以上に正答率を上げていきます。
④過去問まとめ帳:過去問を解いたら必ず、過去問まとめ帳に、共通テストの傾向や対策を書いていきます。書き方は【日本史の共通テスト対策(2)過去問習得法】参照。
(4)目標4:論述対策をする
①過去問:共通テスト過去問や予想問題集で7~8割以上取れるようになったら、もしくは3年夏休みから、2次試験の論述問題過去問を10年分以上解き、模範解答を丸暗記していきます。
最終的には、手に入るだけ、10~20年分以上の過去問を解き、模範解答を丸暗記します。それにより、どういう内容が問われるのか、どういう内容を暗記すべきなのか、どういう解答を書くべきかや、自分に適した論述問題集が分かってきます。
②最善の論述問題対策法:教科書を10~20周以上読んで8割以上暗記し、過去問などの論述問題の模範解答を200以上丸暗記すれば、論述問題の頻出テーマは、ほぼ押さえることができます。
逆に、模範解答を読んで理解するだけでは、全く同じ問題でさえ、合格レベルの論述を書けるようにはなりません。よって暗記するしか上達の道はないのです。
③暗記法:論述問題は、理解しながら【1日10回音読×10日】のように音読すれば、ほぼ丸暗記できます。
④論述問題集2~3冊:過去問を10年分以上暗記したら、過去問と平行して、以下のような問題集から、過去問に傾向(論述の長さ・問題形式)が似た問題が多く入っている問題集を選び、また、傾向が似た他大学の過去問を探し、100~200以上の論述問題を解き、模範解答を丸暗記していきます。
「“考える”日本史論述―「覚える」から「理解する」へ」(河合塾)
「日本史論述演習141」(代ゼミ)
「日本史の論点」(駿台)
「書いてまとめる日本史―日本史短文論述練習帳」(石川晶康著、河合塾)
④過去問まとめ帳:過去問を解いたら、必ず過去問まとめ帳に傾向と対策を書きます。書き方は【日本史の論述対策(3)論述合格戦略】参照。
以上により、志望校の傾向と対策が身を以て深く分かり、論述問題の書き方に慣れ、入試レベルの知識を暗記していくことができます。
(4)目標5:弱点を補強する
過去問(共通テスト、2次論述試験)を解いて気づいた自分の弱点(正誤問題・史料問題、論述問題の弱い時代・分野等)について、既習のテキストを復習したり、他の論述問題集を習得して、知識・理解を強化します。
(5)目標6:長期記憶に入れる
以上を絶えず復習して長期記憶(数ヶ月~数年以上もつ記憶)に入れます。
長期記憶に入れるには、いったん即答できるように暗記してから、2ヶ月以上の復習が必要です。
2.記憶の軸を作る教材
本格的な通史暗記の前に、マンガや概説書を読んでいれば、日本史全体の流れを頭に入れることができます。
【記憶の軸を作るための教材と暗記法】
(1)日本史マンガ
①マンガをオススメする理由:マンガは情報量が少なく、絵があり、読み進めやすく、楽しく学習できるため、暗記しやすいです。
②選択肢:日本史マンガには以下のようなものがあります。
「まんが日本の歴史」(全15巻+別巻4冊、角川)
「学習まんが少年少女 日本の歴史」(全24巻、小学館)
「学習まんが 日本の歴史」(全20巻、集英社)
「学習まんが 日本の歴史」(全20巻、講談社)
「学研まんが NEW日本の歴史」(DVD付、全12巻、学研)
「新マンガゼミナール 日本史」(全2巻、学研教育出版)
「マンガ 日本の歴史がわかる本」(全3巻、三笠書房)
最もオススメなのは「まんが日本の歴史」です。歴史の流れを重視して書かれているので、論述対策にピッタリです。
③暗記法:勉強の合間などに、週10~20冊読むなどし、10周以上読んで、マンガの内容を全て常識にします。「まんが日本の歴史」であれば、10~20週間で10周読んで、ほぼ暗記できます。
④読む時期:マンガといえども結構時間がかかるので、できるだけ1~2年生のうちに読むのが賢明です。
(2)概説書
①選択肢:マンガの次に、もしくは代わりに、以下のような概説書を読むのもオススメです。
「共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる本」(650ページ超、中経出版)
「共通テストはこれだけ! 日本史B 講義編」(全2冊、合計450ページ超、文英堂)
「超速!最新日本史の流れ」(全2冊、合計420ページ、ブックマン社)
「一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書」(352ページ、SB)
「きめる! 共通テスト日本史」(350ページ超、学研)
「教科書よりやさしい日本史」(256ページ、旺文社)
この中で論述問題に適しているのは「超速!最新日本史の流れ」です。教科書より用語の情報量が少なく、歴史の流れがよく分かるようになります。
②暗記法:小説のようにサラサラと【「週1周×10週間」で10周】読むなどして、全てを常識にします。
(3)動画授業
マンガや概説書と並行して、もしくは単独で、スタディサプリなどの動画授業で通史を見ると、通史の理解が進みます。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために、自宅で受講できる【5教科の受験勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【オンライン講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。
3.通史暗記教材と暗記法
3.1.通史暗記戦略
2次試験に論述問題があるといっても、まずは通史暗記をしっかりする必要があります。
日本史の通史暗記戦略には、主に以下のような3つがあります。できれば定期テストで、自分が良いと思った教材・戦略で暗記して、どの教材・戦略が自分に合うか確かめましょう。
【日本史の通史暗記戦略】
(1)通史暗記戦略1:理解用教材+暗記教材
①理解用教材+暗記教材:これが一番ノーマルな暗記戦略です。教科書や参考書のような理解用教材で歴史の流れを理解しながら、暗記教材で用語を暗記します。
定期テストをこの方法で乗り切れているなら、受験勉強も乗り切れます。
②理解用教材:2次試験に論述問題がある国公立大志望者の理解用教材は、教科書1択です。なぜなら、共通テストにしろ、論述問題にしろ、入試に必要な知識は全て教科書に入っており、また、教科書は、論述でそのまま使えるフレーズ・言い回し・文章の宝庫だからです。
ただし、教科書は説明が凝縮されて簡略で、知らない知識が多いと読みにくいので、1~2年生のうちにマンガや概説書を10周以上読んで、大きな歴史の流れ、主な歴史用語を暗記しておくのがオススメです。
③理解用補助教材:教科書が分かりにくいとき、補助として、以下のような、解説が詳しい参考書を使います。オススメは分かりやすい「石川晶康 日本史B講義の実況中継」か最も詳しい「詳説日本史研究」です。
理解した内容を教科書の欄外に書き、情報を集約します。
「共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる本」(650ページ超、中経出版)
「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」(4冊1000ページ弱、ナガセ)
「これならわかる!ナビゲーター日本史B」(4冊1000ページ弱、山川出版社)
「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(語学春秋社)
「詳説日本史研究」(約560ページ、山川出版社)
④暗記教材の選択肢1:流れ&用語本:流れと用語を1冊で暗記できる、以下のような薄めの教材のことです。流れ&用語本では、歴史の流れが簡潔な文章にまとめられ、その中で暗記すべき用語が赤字で書かれており、共通テストレベルの用語と流れをかなり効率的に暗記できます。
「時代と流れで覚える! 日本史B用語」(165ページ、文英堂)
「最速で覚える日本史用語」(207ページ、学研プラス)
「瞬間記憶! つなげて覚える日本史B用語」(224ページ、かんき出版)
「スピードマスター日本史問題集」(122ページ、山川出版社)
「共通テストはこれだけ! 日本史B 講義編」(2冊合計456ページ、文英堂)
「書きこみ教科書 詳説日本史」(山川出版社)
この中では「時代と流れで覚える! 日本史B用語」が最もオススメです。とても薄い問題集でありながら、まとめの図表が豊富で、共通テストレベルの暗記が効率的にできます。暗記法は【「時代と流れで覚える! 日本史B用語」暗記法】参照。
⑤暗記教材の選択肢2:一問一答問題集:暗記用教材としては、以下のような一問一答問題集を使うのが一般的です。
「日本史B一問一答【必修版】」(東進)
「共通テスト 日本史B一問一答【完全版】」(東進)
「山川 一問一答日本史」(山川出版社)
「一問一答 日本史Bターゲット4000」(石川晶康著、旺文社)
「入試に出る 日本史B 一問一答」(Z会)
「共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる一問一答」(角川)
「日本史B一問一答【必修版】」がオススメです。暗記法は【「東進 日本史B一問一答【完全版】」暗記法】参照。
⑥通史暗記法:流れ&用語本や一問一答問題集を20~30ページなどのパートに分け、各パートを1週間前後で15~20周暗記していきます。それと並行して、教科書の該当箇所を週3~5周音読・黙読します。具体的な暗記法は【「東進 日本史B一問一答【完全版】」暗記法】参照。
(2)通史暗記戦略2:教科書を丸暗記する方法
①暗記戦略:教科書を10~20周音読して、歴史の流れも用語も暗記していこうという方法です。暗記のチェックに一問一答問題集や流れ&用語本を、理解の補助に解説が詳しい参考書を用います。
②論述問題対策に有用:論述問題は教科書を理解して暗記していたら書けるので、教科書丸暗記法は論述問題でとても威力を発揮します。
ただし、時間と根気が必要なので、1~2年生のうちにマンガや概説書を10周以上読んで、大きな歴史の流れ、主な歴史用語を暗記しておくのがオススメです。
③暗記法:教科書を10~20周前後音読したら、多くの人は、流れも用語もほぼ暗記できます。具体的な暗記法は【日本史暗記法(3)日本史教科書を丸暗記する方法】参照。
④暗記チェック教材:理解と暗記のチェックのため、上記のような流れ&用語本、一問一答問題集、書き込み教科書(山川教科書の太字部分を穴埋めにした教材)を使います。
オススメは「時代と流れで覚える! 日本史B用語」、「日本史B一問一答【必修版】」です。
⑤理解用補助教材:教科書が分かりにくいとき、補助として、上記のような、解説が詳しい参考書を使います。
オススメは、分かりやすい「石川晶康 日本史B講義の実況中継」か、最も詳しい「詳説日本史研究」です。理解した内容を教科書の欄外に書き、情報を集約します。
(3)通史暗記戦略3:自分でまとめていく方法
①暗記法:定期テスト時に、教科書や参考書を使い、自分で、穴埋め問題形式、もしくは一問一答式にまとめ、暗記している人もいるでしょう。それを入試でも行う方法です。
②オススメしない:自分でまとめるのは、もの凄く時間がかかるので、基本的にはオススメしません。
③活用する方法:定期テスト時に自分がまとめたノートが残っている場合は、それを受験勉強の最初に使って暗記するのは大変役立ちます。
また、覚えにくい箇所や流れを自分の言葉でまとめると、暗記しやすくなるので、暗記の補助としてまとめを使うのは大いに活用すべきです。
3.2.年代・年表・最高権力者の暗記
難関大学志望者は、上記の通史暗記教材を暗記しながら、もしくは通史暗記後、以下の年代と年表、最高権力者名を暗記していきます。
【年代・年表・最高権力者の暗記法・教材】
(1)年代暗記
①年代暗記は有用:直接問われることは少なくても、知っていれば、頭が整理でき、共通テストでも論述試験でも大変役立ちます。
②時期:通史暗記と並行して、もしくは通史暗記後に暗記します。
③選択肢:以下。オススメは、年号だけでなく、将軍や戦乱などのまとめも多い「元祖 日本史の年代暗記法」です。
「元祖 日本史の年代暗記法」(旺文社)
「まんが必修年代暗記法日本史」(文英堂)
「高校 マンガとゴロで100%丸暗記 日本史年代」(受験研究社)
「新 日本史 頻出年代暗記」(学研教育出版)
④暗記法:【「元祖 日本史の年代暗記法」習得法】参照。
(2)年表暗記
①年表:通史暗記中、もしくは通史暗記後に、教科書の巻末にある8~10ページほどの年表(年代、最高権力者名、政治・経済・社会の出来事、文化)を暗記します。
世界の歴史用語は、必要性が低いので、暗記しません。
②メリット:年表を暗記することで、日本史の大きな流れを正確に記憶でき、知識が整理できます。
③暗記法:【日本史暗記法(1)年表暗記法】参照。
(3)最高権力者名の暗記
①最高権力者名:年表に書いてある、平安時代までの天皇名、鎌倉時代以降の将軍・執権名、明治時代以降の首相名を順番に暗記します。
②メリット:最高権力者名を順番に暗記することで、歴史の流れがより明確になります。
③暗記法:【日本史暗記法(1)年表暗記法】参照。
3.3.通史暗記の補助教材
【通史暗記の補助教材】
(1)用語集:意味の知らない用語や初めて見た人物名等は覚えにくいので、用語集で調べ、用語集にマーカーを引き、理解します。そして必要に応じて、要約を自分の暗記教材にメモしておきます。
「日本史用語集」(山川出版社)
「日本史用語集〈究〉」(河合塾)
「日本史用語集」(旺文社)
「必携日本史用語」(実教出版)
一番使われている「日本史用語集」(山川出版社)がオススメです。
(2)史料集:教科書や参考書掲載の史料を読んで意味が分からないとき、日本史史料の解説や現代語訳が載っている以下のような史料集で、理解を深めます。
「詳説日本史史料集」(山川出版社)
「新詳述日本史史料集」(実教出版)
「石川晶康 日本史B講義の実況中継」(史料の現代語訳掲載、語学春秋社)
「日本史史料一問一答【完全版】」(東進)
詳しい「詳説日本史史料集」(山川出版社)がオススメです。
(3)資料集:自分の暗記教材に載っている用語・内容を、資料集の写真・史料・年表で確認することで、視覚的に理解・暗記しやすくなります。
「山川 詳説日本史図録」(山川出版社)
「図説 日本史通覧」(帝国書院)
学校で配られたものがあればそれで良いです。なければ安心の山川の資料集がオススメです。
4.共通テスト対策問題集
共通テストレベルの問題(センター試験過去問、共通テスト過去問、共通テスト予想問題集)で8割以上取れるだけの知識を覚えていないと論述は書けないので、まずは共通テスト対策問題集をどんどん解き、習得し、共通テストで8~9割以上取れる実力を培います。
その後、共通テスト対策を続けながら、論述対策を始めます。
共通テスト対策問題集には以下の4種類があり、優先順位順に書きます。
【共通テスト対策問題集と習得法】
(1)共通テスト過去問問題集
①共通テスト過去問問題集とは:共通テスト・センター試験過去問約15~20年分を時代順・分野別に配列し直して編集した問題集のことです。
②選択肢:以下のようなものがあります。
「ベストセレクション 共通テスト 日本史B重要問題集」(200ページ弱、実教出版)
「共通テストへの道 日本史」(約150ページ、山川出版社)
オススメは「ベストセレクション 共通テスト 日本史B重要問題集」です。「共通テストへの道 日本史」より解説が詳しくなっています。
③最優先:通史暗記後にまず習得すべき問題集は、共通テスト過去問問題集です。共通テストに出そうな重要問題がほぼ網羅されており、過去問より効率良く理解・暗記が進み、日本史の基礎を確立できます。
④習得法:【「ベストセレクション 共通テスト 日本史B重要問題集」習得法】参照。
(2)共通テスト・センター試験過去問
①選択肢:以下のようなものがあります。
「共通テスト過去問研究 日本史B」(教学社)
「共通テスト過去問レビュー 日本史B」(河合塾)
②目標:過去問を10年分以上解いて習得することで、8~9割以上を目指します。
③習得法:【日本史の共通テスト対策(2)過去問習得法】参照。
④過去問まとめ帳:過去問を解いたら必ず、ルーズリーフに過去問まとめ帳を書いていきます。書き方は【日本史の共通テスト対策(2)過去問習得法】参照。
(3)共通テスト形式のオリジナル予想問題集
①選択肢:単元別になっておらず、共通テストと同じ形式です。以下のようなものがあります。
「大学入学共通テスト実戦問題集 日本史B」(駿台)
「共通テスト総合問題集 日本史B」(河合塾)
「東進 共通テスト実戦問題集 日本史B」(東進)
「共通テスト実戦模試(11)日本史B」(Z会)
「大学入学共通テスト 日本史B予想問題集」(角川)
②時期:共通テスト直前に、余裕があれば解いて習得します。
③習得法:形式は共通テスト過去問と同じなので、習得法は【日本史の共通テスト対策(2)過去問習得法】参照。
(4)単元別の問題集
①選択肢:共通テスト・センター試験過去問を主に掲載し、単元別に配列し直した問題集で、以下のようなものがあります。
「大学入学共通テスト 日本史B 実戦対策問題集」(旺文社)
「短期攻略 大学入学共通テスト 日本史B」(駿台)
「ハイスコア! 共通テスト攻略 日本史B」(Z会)
②重要性は低い:共通テスト過去問問題集と内容がかぶり、共通テスト過去問問題集の方が網羅性がありますから、この種の問題集の重要性は低いです。
5.論述対策
具体的な論述対策法は【日本史の論述対策(3)合格戦略】に書いています。
6.終わりに
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
皆さんが日本史を得意科目にするのに、この記事が参考になれば幸いです。
創賢塾のホームページに書かれた勉強法をいち早く習得したい高校生のために、自宅で受講できる【5教科の受験勉強法を習得する3ヶ月自宅集中セミナー】【長期勉強法コース】を開講しています。【オンライン講座・セミナー一覧】はこちら。関心ある方はご参照ください。